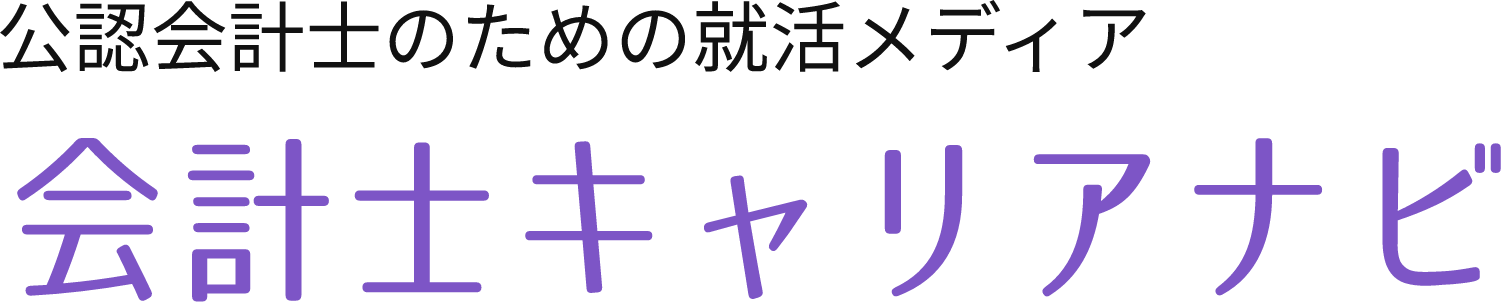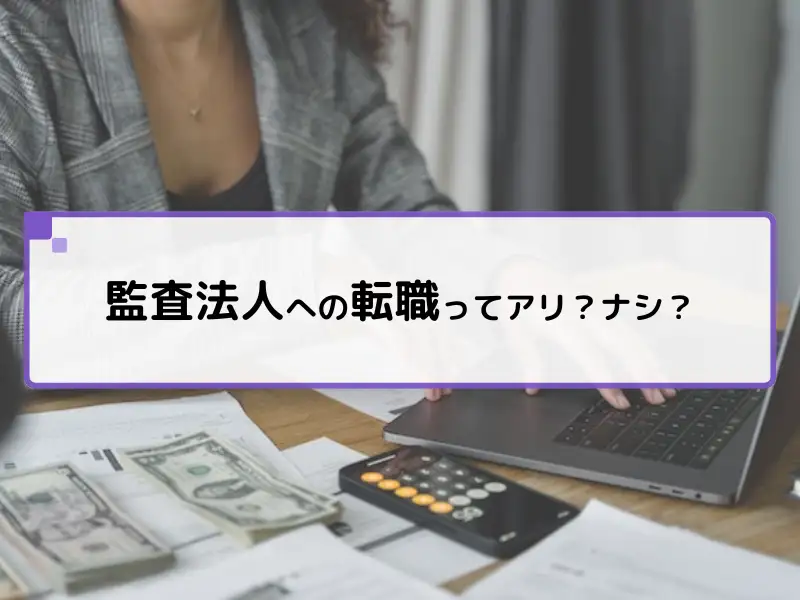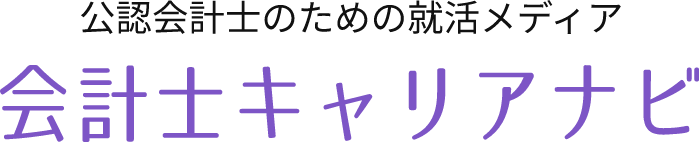「監査法人って、本当に転職先としてアリなの?」
「最初に監査法人に行くべきか、別のキャリアを選ぶべきか迷っている…」
公認会計士試験に合格したばかりのあなたにとって、最初のキャリア選択は将来を大きく左右する大事な一歩です。特に、監査法人は“王道ルート”と言われる一方で、「激務」「すぐ辞めたくなる」などのネガティブな声も多く、迷うのは当然のこと。
この記事では、そんなあなたの疑問に答えるべく、
- なぜ多くの合格者が監査法人を選ぶのか
- 転職先としてのメリット・デメリット
- 監査法人が“アリ”な人、“ナシ”な人の特徴
といったテーマを、現場のリアルも交えながら徹底解説していきます。
監査法人に行くべきかどうか、あなたにとっての“正解”が見えてくるはずです。
目次
公認会計士にとって監査法人は王道?

「とりあえず監査法人」は正解?間違い?
公認会計士試験に合格した人の多くがまず目指すのが「監査法人」への就職です。就職サイトや予備校でも“最も王道の進路”として紹介されることが多く、疑問を持たずに選んでしまう人も少なくありません。
しかしその一方で、「やりがいが感じられない」「数年で辞めたい」といった声も多く聞かれます。ではなぜ、これほどまでに監査法人が“王道”とされるのでしょうか?その実態と背景を見ていきましょう。
監査法人の主な役割と公認会計士との関係
監査法人とは、上場企業や大規模法人の財務諸表に対して第三者の視点から適正性を検証する機関です。
公認会計士が所属し、主に企業の決算書を精査して「正しく作られているかどうか」を監査意見として表明するのが主業務。企業の信頼性を担保するうえで重要な社会的責任を担っています。
この仕事を通じて、会計士は会計基準、内部統制、リスクアプローチ、ヒアリング力、文書化スキルなど、あらゆる専門スキルを短期間で習得できます。特にBIG4監査法人(EY新日本、あずさ、トーマツ、PwC)では、国際監査基準に基づいた実務経験を積めるため、世界中で通用するスキルセットが身につくのも魅力です。
また、若手でも大手上場企業を相手に仕事をするため、仕事のスケールが大きく、知的好奇心を刺激する環境でもあります。
初任給やキャリアスタートとしての魅力
監査法人の魅力の一つは「敷居の低さ」と「教育の厚さ」です。会計士試験に合格すれば、実務経験がなくても正社員として雇用され、しっかりと教育される環境が整っています。
給与面でも恵まれており、初年度から年収500〜600万円に到達する例も珍しくありません。加えて、残業代・繁忙期手当・住宅手当などの福利厚生も手厚いため、初任給以上の収入を得ている若手も多くいます。
さらに、OJTや社内研修が非常に充実しており、「新人教育」にリソースを割くカルチャーが根付いています。毎年のように新卒・未経験者を大量採用しているため、教育体制が体系化されており、未経験でも着実に成長できる環境です。
なぜ多くの合格者が監査法人を選ぶのか
最も大きな理由は、「間違いのないスタート」が切れるという安心感です。
監査法人に就職すれば、「職歴に傷がつくことはない」「転職時に評価されやすい」という前提があり、“キャリアの土台”として非常に堅牢です。特に20代前半のうちは、将来の可能性を広げるという意味でも、評価の高い職歴が得られる監査法人は強力な武器になります。
また、周囲に同世代の公認会計士が多く、相談できる同期や先輩が豊富にいることも大きな魅力です。わからないことも聞きやすく、心理的な不安が少ないため、初めての職場としては申し分ない環境といえるでしょう。
さらに、監査法人で数年経験を積んだ後、事業会社やコンサルティングファーム、海外駐在、フリーランス会計士といった多彩なキャリア選択が可能になります。
ただし、全員にとって“ベスト”とは限らない
ただし、注意すべき点もあります。いくら「王道」とはいえ、仕事の性質が自分に合っているとは限りません。ルーティンが多く、繁忙期は非常に忙しいため、「頭を使う仕事がしたい」「もっと主体的に経営に関わりたい」といった志向の人にはギャップを感じることもあります。
また、近年では入社から2〜3年で転職・離職する若手も非常に多く、「とりあえず入ったけど、何がしたいかわからなくなった」という声も耳にします。
つまり、「王道=最適解」とは限らず、自分の価値観やキャリアビジョンに照らして選ぶことが重要なのです。
次の章では、転職市場における監査法人の価値や位置づけをさらに深掘りしていきます。
転職市場での監査法人の位置づけ

「監査法人出身者は転職市場でどう評価されるのか?」
会計士としての最初のキャリアを監査法人で積んだ後、その経験が市場でどう活かせるのかを知ることは、将来のキャリア設計において重要です。この章では、転職市場における監査法人の価値、採用のタイミング、そして求められるスキルについて詳しく解説します。
監査法人は転職先としてどう見られている?
監査法人は、実は転職先としても一定の人気を誇る存在です。
特に中堅〜ベテランの会計士が「再び監査に携わりたい」と考えるケースや、USCPAなど海外資格を持つ人がグローバル案件を求めて転職するケースが見られます。
転職市場における監査法人の評価は主に次の3点に集約されます。
- 専門性が高い:監査法人での経験は、財務諸表を深く読み解き、企業のリスクを見抜くスキルの証明になります。
- ロジカルシンキングに強い:監査調書の作成やクライアントとのやりとりを通じて、論理的な説明力が養われることが評価されています。
- 信頼のある経歴:特にBIG4出身者は、「一定レベルの教育・スキル・人間力が保証されている」とみなされることが多く、ファーム名自体が「ブランド」として機能します。
一方で、「業務が限定的すぎる」「自走力に欠ける」といった懸念が示されるケースもあり、評価は一様ではありません。
経験者採用の実情とタイミング
監査法人自身も、転職市場において“採用する側”として活発に動いています。
特に以下のようなタイミングで経験者採用が増える傾向にあります。
- 12月〜3月の繁忙期直前:年明けからの監査繁忙期に備えて、即戦力となる人材を急募するケースが多く見られます。
- 人事異動や退職が続く6月〜8月:中堅層が抜ける時期に合わせ、リーダー層を補充する目的で経験者採用を行うケースもあります。
- IPO・グローバル対応案件の増加:上場準備企業や海外展開企業を担当するチームで人手不足が生じたときは、USCPAや英語に強い人材が優先的に採用されます。
なお、中途採用は「年中通して常に募集している」状態に近くなっており、希望のタイミングでチャンスを見つけやすいのも特徴です。特にコロナ以降は働き方の多様化が進み、時短勤務やフレックスタイム制度を活かして再チャレンジする人も増えています。
中途採用で評価されるスキルとは
転職市場において「監査法人出身者=万能人材」と見なされるわけではありません。
評価されるかどうかは、スキルやマインドセットに大きく左右されます。
以下は、監査法人出身者が「転職市場で評価されやすいスキル」の代表例です。
- 複数社を横断して見られる「俯瞰力」 監査法人では様々な業種・規模のクライアントに関与するため、「比較して判断する力」や「業界ごとの特徴を掴む力」が培われます。これが事業会社やコンサルで重宝されます。
- 資料作成力とロジカルなプレゼン力 監査調書の作成や、監査チーム内でのプレゼン、クライアント説明などを通じて、ドキュメント作成スキルと説明力が磨かれます。コンサルティングや戦略部門で高く評価される資質です。
- 責任感とチームマネジメント シニアスタッフ以上になると、複数人のチームを管理し、クライアントとも密にやり取りする経験を積みます。これがマネージャークラスでの転職時に大きな武器となります。
一方で、「自ら動く力(セルフスターター性)」「スピード感」「変化対応力」など、監査法人では育ちにくい部分をどう補完するかが転職成功のカギとも言えます。
このように、監査法人出身者は高い専門性と信頼性を武器にしつつ、自らの強みをどう言語化・発揮できるかによって、転職市場での評価が大きく変わります。
監査法人に転職するメリットとは

「転職先としての監査法人には、どのような魅力があるのか?」
一度キャリアを始めた後、あらためて監査法人への転職を考える人も少なくありません。ここでは、他業界から監査法人へ転職する際の主なメリットを3つの視点から解説していきます。
専門性を磨ける環境が整っている
監査法人は、プロフェッショナルとしての基礎体力を鍛える最適な場です。
日々の業務は、財務諸表の監査や内部統制の評価など、高度な専門知識が求められるものばかり。ここでの経験は「財務のプロフェッショナル」としてのキャリアの土台を作ることに直結します。
さらに、監査業務は形式的なルーチンワークと思われがちですが、実際にはクライアントごとの状況や業界動向を踏まえた判断力と応用力が必要です。そのため、金融・不動産・製造業など幅広い分野の業務知識が自然と身につくのも大きな利点です。
また、研修制度が非常に充実しており、入社後も段階的にスキルアップが可能です。USCPAやIFRSなどの資格取得支援も整っているため、「手に職をつけたい」「国際的に通用するスキルを得たい」と考える人にはぴったりの環境です。
ネームバリューがその後のキャリアに有利
BIG4をはじめとした監査法人のブランド力は、転職市場で非常に強い武器となります。
例えば、EY・PwC・Deloitte・KPMGといった名前は、経理・財務・M&A関連の求人票でも一目置かれる存在です。履歴書にこれらの法人名が記載されているだけで、「一定の水準を満たした人材」という評価を受けやすくなります。
また、監査法人では常にチームプレーが求められるため、プロジェクトマネジメントやリーダーシップの経験を積むことも可能です。こうした経験は、将来的に事業会社の経営企画や内部監査部門、コンサルティングファームへの転職時に大きなアピールポイントになります。
特に若手のうちに監査法人の名刺を持つことで、「キャリアの選択肢を広げやすい」という戦略的な価値を見出す人も増えています。
海外案件・IPO監査など幅広い経験が可能
監査法人ならではの醍醐味の一つが、「非日常的なプロジェクトへの関与」です。
たとえば、上場企業の監査に加えて、以下のようなプロジェクトに関わることも可能です:
- IPO監査:未上場企業の上場準備を支援するプロジェクトでは、会社の内部体制構築や開示資料の整備といった幅広い業務に携われます。
- 海外案件:外資系クライアントやグローバル展開している日系企業の監査では、英語を使った監査調書の作成や海外チームとの連携なども発生し、国際的なビジネス経験が積める点が魅力です。
- デジタル・ESG監査:近年では、IT監査やESG関連のアドバイザリーも急増しており、新たな専門分野を開拓したい人にとって大きなチャンスがあります。
これらの経験は、他業種ではなかなか得られない横断的かつ先端的なスキルセットを形成するのに役立ちます。
以上のように、監査法人への転職は「成長の場」としても「キャリアブランディングの場」としても非常に価値がある選択肢です。特に専門性や国際経験を武器にしたい人にとっては、他にない環境と言えるでしょう。
監査法人への転職が向かないケース

すべての人にとって監査法人がベストな職場とは限りません。
どれだけ待遇やネームバリューが魅力的でも、向き・不向きは確実に存在します。ここでは、転職後にギャップを感じやすいケースを整理し、事前にチェックすべきポイントを解説します。
激務や繁忙期に耐えられないとつらい?
監査法人の実態としてよく話題に上がるのが、「繁忙期の激務」です。
特に12月決算企業が多い日本では、1月から3月が監査法人の繁忙期となり、深夜までの残業や休日出勤が発生するケースも珍しくありません。
この時期は、クライアントの提出資料の確認、監査調書の作成、レビュー対応などが同時並行で進み、精神的にも体力的にもタフさが求められるのです。
「ワークライフバランスを重視したい」「定時退社が大前提」という価値観の人にとっては、想像以上にストレスが大きい可能性があります。もちろん、最近では働き方改革の一環として業務量の平準化が進んでいますが、完全に解消されたとは言い切れない現実があります。
型にはまった業務にストレスを感じる人へ
「自分で意思決定したい」「自由に仕事を進めたい」タイプの人は要注意です。
監査業務は、公認会計士としての職業的専門性と独立性が最優先されるため、仕事の進め方にも一定のルールと型があります。これは品質を保つために必要な仕組みですが、人によっては「細かすぎる手続き」や「チェック文化」が負担に感じるかもしれません。
特に、創造的な仕事やスピード感を重視する人にとっては、監査法人の仕事は「決まったフレームで進む反復業務」として映ることも。
実際には、クライアントや業界ごとに対応が異なり応用力も求められるのですが、初期段階では単純作業が多く感じることもあるため、モチベーションの維持に苦労する人もいます。
転職後すぐに辞める人の共通点とは
せっかく監査法人に転職したのに、1年以内に辞めてしまう人もいます。
その多くが口にするのが、「思っていたよりも地味」「成長が実感できない」「人間関係がドライすぎる」といった、カルチャーギャップに起因する理由です。
監査法人は、企業の信頼性を担保する立場にあるため、成果よりもプロセス重視の文化があります。また、社内ではレビュー→差し戻し→修正という流れが日常的であり、フィードバックが厳しめであることも多いのです。
さらに、クライアント先常駐やリモート業務が多く、社内交流の機会が少ないと感じる人もいるでしょう。こうした点を知らずに入社すると、「何のために仕事してるのかわからない」と早期離職の引き金になりやすいのです。
監査法人への転職が自分にとってベストな選択肢かを判断するには、「どんな働き方をしたいか」「何にやりがいを感じるか」という軸を持つことが重要です。
次の章では、その判断に役立つ具体的な視点を紹介していきます。
監査法人に転職すべきか迷ったときの判断軸

「監査法人に転職して後悔しないか?」と悩む方も多いでしょう。
実際、待遇や安定性は魅力的でも、自分の価値観やキャリアプランと合致していなければ、早期離職のリスクもあります。この章では、転職前に押さえておきたい判断基準を3つご紹介します。
自分のキャリアビジョンとの一致がカギ
転職で最も重要なのは、目先の条件ではなく「その後のキャリアとの整合性」です。
監査法人での業務は、会計・財務のプロフェッショナルとしての基礎体力を高める場でもあります。将来的にCFOや経営企画、独立開業、コンサルタントなどを目指す場合、監査法人での経験は強力な武器になるでしょう。
一方、マーケティングや営業など数字とは異なる分野に進みたい場合は、転職後のキャリアとの接続が難しくなる可能性もあります。3年後・5年後にどうなっていたいかを明確にし、監査法人での経験がその目標にどう寄与するのかを考えることが大切です。
他の選択肢(事業会社・コンサル)との比較
監査法人だけが会計士の活躍の場ではありません。
同じ資格やスキルを活かせる転職先として、事業会社の経理財務部門や、戦略・財務系のコンサルティングファームなども挙げられます。
事業会社では、内部視点からの経営サポートや実務に密着した会計業務に関わることができ、より主体的な判断や改善提案の経験を積むことが可能です。
一方、コンサルでは、課題解決や提案力、論理的思考力が問われる環境であり、スピード感やプレッシャーも大きいですが、高い報酬と多様な経験が得られます。
それぞれの環境における学びの質、キャリアの広がり方、働き方の違いを比較し、自分に合った場所を見極めることが必要です。
後悔しない選択をするためのチェックリスト
「やっぱり思っていたのと違った…」とならないために、事前の自己分析は不可欠です。
以下のような観点で、転職先として監査法人が合うかどうかを冷静に見極めましょう。
- 働き方の希望(定時で帰りたい/成長重視/年収重視 など)
- 業務内容への興味(会計・監査・ルールに関心があるか)
- 将来なりたい姿(独立・出世・専門職志向など)
- 人間関係のタイプ(縦社会に抵抗がないか、個人主義かチーム志向か)
このようなチェックポイントを事前に整理し、自分の価値観や理想とズレがないかを確認することで、後悔のない転職判断ができるはずです。
転職は人生の転機。
監査法人という選択肢があなたにとって「あり」なのか「なし」なのかは、自分自身をどれだけ深く理解しているかによって変わってきます。
まとめ:監査法人への転職は「アリ」か「ナシ」か、あなた自身の答えは見つかりましたか?

この記事を通じて、あなたが抱えていた「監査法人への転職は自分に合っているのか?」という疑問に対して、ヒントや判断材料を得ることはできたでしょうか?
監査法人は、公認会計士にとって王道のキャリアであり、専門性や信用力を高めるための絶好の環境です。一方で、激務や画一的な働き方への懸念があるのも事実です。
転職市場ではそのスキルや経験が高く評価される一方で、自分のキャリアビジョンとマッチしなければ後悔する可能性もある──その両面を正しく理解した上で、ご自身に合った選択肢を選ぶことが最も重要です。
もしまだ迷いがあるなら、ぜひ今回の記事の中で紹介したキャリアビジョン・比較検討・チェックリストを改めて振り返ってみてください。
監査法人は「万能な場所」ではなく、「合う人には非常に強い武器になる場所」です。あなたの志向や未来像と照らし合わせながら、納得のいく一歩を踏み出しましょう。
あなたの転職活動が、後悔のない、前向きな決断となることを心から願っています。