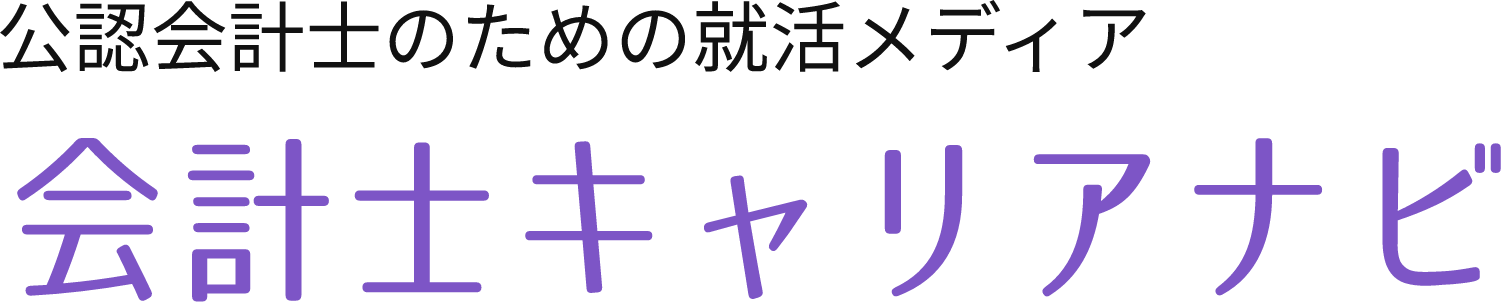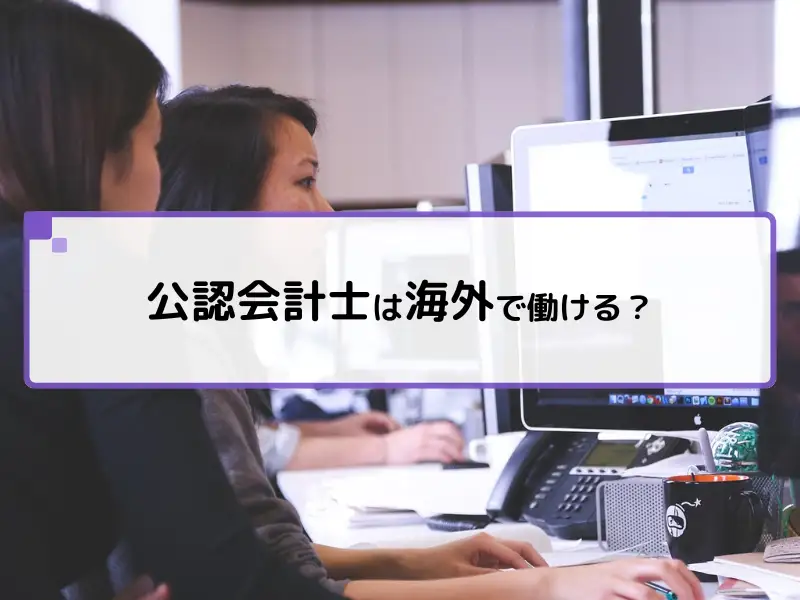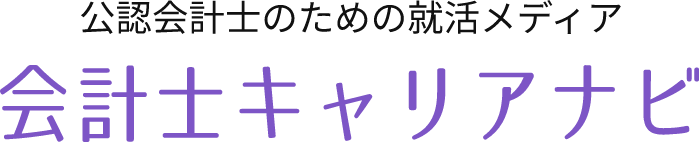「公認会計士って、海外でも通用するのかな?」
「海外で働きたいけど、資格や語学ってどれくらい必要なんだろう?」
こうした疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。特に、公認会計士試験に合格したばかりのあなたにとって、「どんなキャリアが待っているのか」「海外での活躍は現実的なのか」は気になるテーマです。
この記事では、「公認会計士が海外で働くための現実と準備」に焦点を当てて解説していきます。実際に活躍する人の事例、必要なスキル、監査法人で得られる経験など、将来の選択肢を広げる情報が満載です。
「グローバルに働きたい」と思ったとき、どんなルートがあるのか。この記事を読むことで、その道筋が見えてくるはずです。それでは、まず「本当に海外で働けるのか?」という問いから見ていきましょう。
目次
公認会計士は本当に海外で働けるのか?

「日本の公認会計士資格で、海外で本当に働けるのだろうか?」と疑問を持つ人は多いでしょう。確かに、監査や会計の分野は国ごとに制度や規則が異なるため、日本国内の資格がどの程度海外で通用するかは気になるポイントです。本章では、公認会計士が海外で活躍する実例や、日本資格の適用範囲、そしてUSCPAや現地資格との違いについて整理していきます。
国際的に活躍する公認会計士の実例
実際に日本の公認会計士資格を持って、海外で活躍する人は少なくありません。たとえば、以下のようなケースがあります。
- 監査法人で働き、ロンドンやシンガポールに赴任
- 日本企業の海外現地法人でCFOや財務マネージャーとして勤務
- 海外進出支援やクロスボーダーM&Aを扱うコンサルファームで国際案件を担当
これらの人々は、日本国内での監査や会計経験をベースに、海外でのキャリアを切り開いています。特に国際会計基準(IFRS)や内部統制、グローバル監査対応経験がある人は、海外からも高く評価される傾向にあります。
日本の資格で海外就職する難易度
ただし、「日本の公認会計士資格だけ」で現地採用されるのは簡単ではありません。なぜなら、国ごとに公認会計士の制度が異なるため、現地企業が日本資格だけで採用するのは稀だからです。
主な壁は以下の通りです:
- 各国で異なる会計基準・税務制度の知識が必要
- 日本資格は現地では資格認定されないケースが多い
- 英語での専門業務遂行力が問われる
したがって、海外赴任を経て現地で経験を積むルート、もしくは追加で現地資格(例:USCPA)を取得するルートが現実的です。
USCPAや現地資格との比較と違い
海外で働くためには、日本の公認会計士(JCPA)と他国資格との違いを理解することも大切です。ここでは代表的な資格であるUSCPA(米国公認会計士)と比較してみましょう。
| 項目 | 日本の公認会計士(JCPA) | USCPA |
| 対象範囲 | 日本国内が中心 | 国際的に広く認知 |
| 試験言語 | 日本語 | 英語 |
| 資格取得難易度 | 非常に高い | 高いがJCPAより短期間で取得可 |
| 活躍フィールド | 監査法人、事業会社、日本市場中心 | 外資系、海外市場、グローバル企業 |
USCPAは、英語での試験である点と、国際的な認知度が高い点で、グローバルキャリアを志向する人に適しています。一方、日本の公認会計士は、日本国内における実務経験の深さや、制度会計への理解力が武器となります。
そのため、「海外で働く=USCPA必須」というわけではありませんが、USCPAは海外就職・海外駐在のパスポート的役割を果たすため、キャリアの幅を広げる選択肢として検討する価値があります。
日本の資格だけで海外に挑戦することは難しいかもしれませんが、現実には多くの会計士がグローバルに活躍しています。次章では、実際に海外で働くために必要なスキルや準備について、より具体的に見ていきましょう。
海外で働くために必要なスキルと経験

「海外で働きたい」と考える公認会計士にとって、語学力や異文化対応力、自己アピール力は欠かせません。海外勤務では、日本と同じスキルセットでは通用しない場面も多く、現地に溶け込みながら結果を出せるかが問われます。この章では、実際に海外で活躍するために必要なスキルと、それらをどう準備すればいいかについて整理していきましょう。
語学力(特に英語)はどこまで必要?
求められる英語レベルはポジションや役割によって異なります。
- 初期段階(スタッフ〜シニア)
→ TOEIC700〜800点程度が目安。意思疎通がスムーズであればOK。 - マネージャー以上の職位
→ プレゼン力、ネゴシエーション力が問われ、ビジネス英語での即応力が求められます。
加えて、監査・会計用語に精通した英語を使えるかどうかも重要です。たとえば、“materiality”(重要性の基準値) や “subsequent event”(後発事象) など、専門用語を正しく理解し使いこなせるかがポイントとなります。
異文化コミュニケーションと業務適応力
英語力以上に重要視されることが多いのが、異文化適応力です。現地の価値観や働き方、上司・部下との距離感などが日本とは大きく異なるため、柔軟に対応できるかどうかが問われます。
例えば:
- 欧米では、個人の主張や判断が重視される
- アジア圏では、上下関係よりチームワークを重視する傾向がある
- 日本と違い、成果主義の評価制度が一般的
こうした環境のなかで、自分のスタイルを調整しながら、現地のやり方に敬意を払いつつ成果を出す姿勢が求められます。
さらに、チーム内での信頼関係を築くためには、文化的な違いに対する理解と、謙虚さを持った対話力が不可欠です。
海外経験がない人がアピールすべきこと
「海外で働いたことがないと無理では?」と思われがちですが、国内経験だけでも十分に評価されるポイントがあります。実際、海外赴任を果たした若手会計士の多くは、以下のようなアピールポイントを持っていました。
- 多国籍企業や外資系企業の監査・税務経験がある
- 英語を使った業務経験(資料作成・メール・会議など)
- IFRSやUS GAAPなど国際会計基準の知識がある
- 若手ながら積極的にチーム内で発言・改善提案をしてきた
たとえ英語が完璧でなくとも、積極性や論理的思考、誠実な対応力などがあれば、海外現地でも信頼を得やすくなります。
語学力と異文化対応力を高め、自分の強みを明確に伝えられる人材こそが、海外でのキャリアを切り開いています。次章では、そうしたスキルを活かして監査法人でどのように海外キャリアを構築していけるかを見ていきましょう。
監査法人での海外キャリアのリアル

海外で働く公認会計士にとって、監査法人でのキャリアは最も現実的かつ戦略的な選択肢です。世界各国に広く展開しているグローバルアカウンティングファームは、国際的な人材流動性が高く、若手にも海外勤務のチャンスが与えられています。この章では、監査法人における海外キャリアの実態を詳しく解説します。
グローバルアカウンティングファームの海外赴任制度とは?
グローバルアカウンティングファームには、それぞれ「グローバルモビリティプログラム」という海外赴任制度が存在します。一定の年次・評価を経た社員に対して、現地オフィスでの勤務やプロジェクト参加の機会を提供する制度です。
一般的な流れは以下の通りです:
- 国内オフィスで数年の経験を積む(目安3〜5年)
- 語学力・評価・マネジメント能力などを考慮し選抜
- 期間は1〜3年、国によっては延長や現地採用への切り替えも可能
- 帰国後は海外経験を活かし、マネージャーや専門部署に登用されることも多い
こうした制度は、単なる「観光的な勤務」ではなく、真の国際経験を積む修業の場として機能しています。
駐在と現地採用の違いとメリット・デメリット
海外での勤務形態は、大きく分けて駐在(社内制度による派遣)と現地採用(海外法人に直接就職)の2種類があります。
| 比較項目 | 駐在 | 現地採用 |
| 給与 | 日本の水準+海外手当 | 現地水準(国によって差が大) |
| 福利厚生 | 社宅・保険・子女教育支援などが手厚い | 自己負担が多く、待遇に差が出やすい |
| ビザ | 法人側が手配・サポートあり | 自力での取得・エージェント活用が必要 |
| 任期 | 2〜5年の期限付きが多い | 無期限も可、ただし競争は激しい |
駐在は待遇面で有利ですが、異動リスクや任期満了の不安があります。一方、現地採用は定着できれば自由度が高い反面、ハードルも高めです。
若手のうちに海外を目指すルート
若手会計士が海外勤務を目指す場合、以下のようなルートがあります:
- グローバルアカウンティングファームでキャリアをスタートし、社内制度で海外赴任を狙う
- 入社前から英語対応部署(外資系被監査会社担当)に希望を出す
- IFRSやUS GAAPなどの国際業務を積極的に経験し、アピール材料にする
- USCPAやMBAなど、海外で通用する資格取得も視野に入れる
また、若手のうちに以下を意識すると有利です:
- 英語での資料作成やミーティング経験を積む
- グローバル人材育成プログラムへの参加
- 海外案件に積極的に志願する姿勢を見せる
若いうちから国際志向をアピールしておくことが、海外キャリアへの近道になります。
監査法人で働くことは、海外を目指す上で現実的かつ戦略的なルートです。次章では、監査法人を経由せず、現地での就職を目指す場合に必要な準備について解説します。
現地就職を目指す場合の準備と戦略

監査法人を経由せず、海外で直接会計士として就職するルートも存在します。とくに「海外で腰を据えて働きたい」「将来的に永住や独立も視野に入れている」など、長期的な視点を持っている人にとって、現地就職は魅力的な選択肢となります。ただし、日本の資格でそのまま採用されるケースはまれで、事前の綿密な準備と戦略的なアプローチが求められます。
就職先の探し方とビザの壁
まず初めに立ちはだかるのが、ビザの取得と就職先の見つけ方です。日本での転職活動とは大きく異なり、海外では雇用主がビザのスポンサーとなる必要があります。
就職先の探し方のポイント:
- LinkedInなどのグローバル求人サイトを活用
- 現地の求人メディア(例:Indeed US/UK、Seek(豪州)など)を定期的にチェック
- ターゲット国で活動している日系企業や会計事務所を狙う
- 現地での就職フェアやオンラインキャリアイベントに参加
ビザに関しては、以下のような難点があります:
- 現地会計資格がないとビザスポンサーが難しい国が多い(例:アメリカ、カナダ)
- 就労ビザ発行にあたって最低年収や経験年数の条件が設けられている場合もある
- 留学を経て現地資格を取得し、現地就労ビザを申請するという回り道も多い
「就職のハードル=ビザのハードル」と考えて対策を立てることが重要です。
グローバル転職エージェントの活用法
個人で現地就職を目指すには限界があります。そこで頼りになるのが、グローバル対応の転職エージェントです。
代表的な会計士向けエージェント:
- JAC Recruitment(アジア中心)
- RGF(アジア・北米・欧州)
- Michael Page(グローバル展開)
- Robert Walters(英語圏中心)
これらのエージェントを活用するメリットは以下の通り:
- 現地法人とのネットワークを持ち、非公開求人も紹介される
- ビザの条件やサポート体制をあらかじめ確認できる
- 現地の給与水準や職場文化についても詳しいアドバイスが得られる
- 英語での履歴書・職務経歴書の添削も対応可能
エージェントとの関係構築は、海外就職の大きな突破口になります。
必要書類やレジュメの国際基準とは?
日本の就活とは異なり、海外では書類選考が非常に重要です。しかも書式・内容・ボリュームすべてにおいて「日本式」とは異なる常識が存在します。
レジュメ作成のポイント:
- A4 1枚に収まる簡潔な「Resume」形式(日本の職務経歴書とは異なる)
- 実績・成果・数字を中心に表現
- 職歴のギャップや転職理由も明確に記載する
- 志望動機よりもスキル重視、特に国際基準の業務経験が評価される
また、合わせて以下も準備が必要です:
- 英文のカバーレター(志望動機)
- TOEIC/IELTSなどの語学スコア
- LinkedInプロフィールの整備
- 現地会計資格の取得進捗や意欲の表明
「書類の完成度=チャンスの広がり」ですので、プロの添削やアドバイスを受けるのも効果的です。
現地就職は簡単な道ではありませんが、準備と戦略次第で確実に道は開けます。次章では、こうした現地就職ルートを踏まえた上で、あらためて監査法人を出発点とすることの意義について解説していきます。
海外キャリアを見据えた就職なら監査法人へ

「将来、海外で働きたい」と考える公認会計士試験合格者にとって、最も現実的かつ効果的な第一歩は監査法人に就職することです。とくにBIG4と呼ばれる大手監査法人は、グローバルネットワークを活かした海外キャリア支援の制度や機会が豊富であり、「いずれは海外」という目標の実現に向けた最短ルートとなり得ます。
多国籍被監査会社と働く経験が得られる
まず注目すべきは、多国籍企業や外資系被監査会社を担当するチャンスの多さです。大手監査法人では以下のようなグローバル企業を被監査会社として抱えており、英語を使った実務経験を積む機会が自然と発生します。
- 外資系製薬企業やメーカー
- グローバルIT企業
- 海外進出している日本企業の現地子会社
- 海外ファンド傘下の企業 など
このような環境で働くことで、
- 英語での監査調書作成や会議参加
- 国際会計基準(IFRS)への理解
- 海外チームとの連携経験
といったスキルが身につきます。実践的な「海外対応力」は監査法人でこそ磨かれるのです。
将来の武器になる「海外対応力」とは
監査法人で働くことで得られる「海外対応力」は、単に英語力だけではありません。以下のようなビジネススキル・マインドセットが養われます。
- マルチカルチャー環境でのコミュニケーションスキル
- タイトな期限の中でも品質を保つ業務遂行力
- 現地の会計士・弁護士との協業経験
- 国際税務や移転価格など、海外特有の論点への理解
このようなスキルは、現地就職・独立・外資転職・MBA進学など、あらゆる将来設計において武器になります。
さらに、海外対応力が高いと以下のような選択肢が現実味を帯びてきます:
- 海外駐在員としての抜擢
- グローバル案件の責任者
- 海外進出を目指す企業への転職
- 日本と海外をつなぐコンサルタントとしての独立
どの道を選んでも、自信を持って進める素地が整うのです。
グローバル人材への第一歩として最適な理由
海外を目指す上で監査法人が優れている最大の理由は、「グローバル人材」としてのスタート地点を提供してくれることです。以下のような制度や風土が、その背景にあります。
- 海外赴任制度の整備(2〜5年の駐在)
- 社内英語研修・留学制度の充実
- 年齢や役職に関係なくチャレンジを後押しする文化
- 国際的なプロジェクトに若手でも参加可能
また、監査法人でキャリアをスタートすれば、日本公認会計士としての経験を積みつつ、USCPAや現地資格へのステップアップも可能です。現実的には以下のようなルートが考えられます:
- 日本で監査法人に入所し、2〜3年実務経験を積む
- 英語力や国際案件の経験を積む
- 海外赴任やUSCPA取得、現地資格取得にチャレンジ
- 海外就職や現地転職、国際的なキャリアパスへ展開
このように、「監査法人での経験」は海外キャリアへの最短かつ確実なルートといえるのです。
海外での活躍を夢見るあなたにとって、監査法人という環境は理想的なスタート地点となるでしょう。次に進むべきは、その環境をどう活かすかを考えることです。
まとめ

「公認会計士として海外で働きたい」という夢は、決して遠いものではありません。語学力や経験はあとからでも身につけられますが、実務の基盤がなければ始まりません。その意味で、監査法人はまさに最適なスタート地点です。
多国籍被監査会社との実務、海外赴任制度、英語環境での成長機会。これらはすべて、グローバルキャリアを志す人にとって価値のある財産となるはずです。まずは日本で実務経験を積み、その先のキャリアを世界に広げていきましょう。