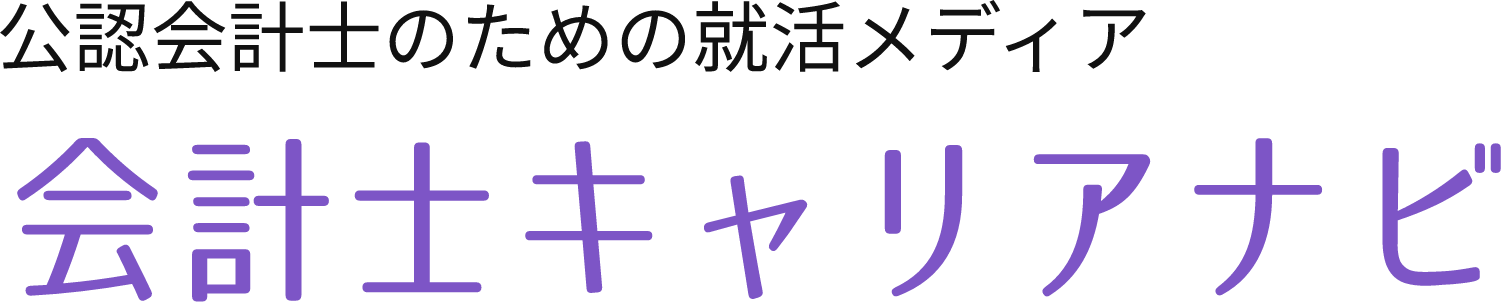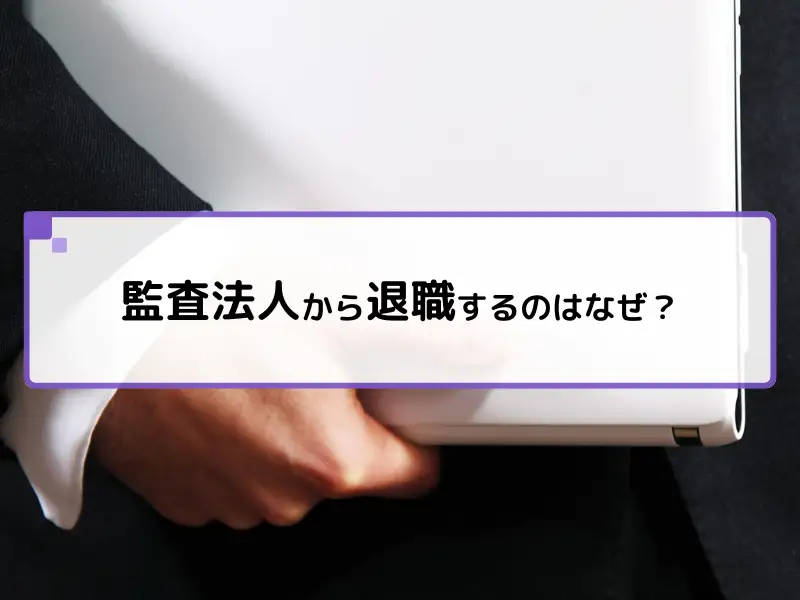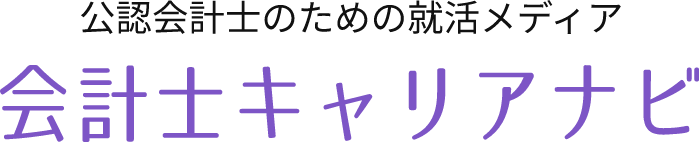「監査法人って、なんでそんなに人が辞めるの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
公認会計士試験に合格し、これから監査法人への就職を考えているあなたにとって、「退職者が続出」というネットの声は不安の種かもしれません。SNSで流れる「もう辞めたい」「激務すぎて限界」という声を目にすれば、「自分はやっていけるのか」と心配になるのも当然です。
でも、果たしてそれは業界全体の真実なのでしょうか?
あるいは、特定の時期や環境に限った話なのでしょうか?
この記事では、監査法人で退職者が続出すると言われる背景や理由を客観的に解説しつつ、法人ごとの違いやポジティブな転職事例、そして監査法人で働き続けることのメリットまで網羅的に紹介します。
「辞めたくなる理由」だけでなく、「辞めない選択」や「活かし方」まで含めて、あなたのキャリアにとって本当に価値ある選択肢を一緒に考えていきましょう。
目次
そもそも監査法人で「退職者が続出」と言われる背景とは?

「監査法人は人がすぐ辞める」という声をよく耳にしますが、それは一体なぜなのでしょうか?
この見出しでは、若手会計士を中心に「退職者が続出」と見られてしまう背景について、多角的に解説していきます。
若手が感じるギャップと現場のリアル
監査法人に入社する多くの若手会計士は、「プロフェッショナルとしてスキルを磨きたい」「高度な知見を活かした仕事がしたい」という強いモチベーションを持っています。
しかし、入社後に任される仕事の多くは、監査調書の入力や資料の突合、チェックリスト作業などルーティン化された作業が中心。
「想像していた仕事と違う…」という理想とのギャップに直面し、モチベーションを失ってしまう若手も少なくありません。
特に1年目~3年目までは「地味な作業が延々と続く」と感じる時期であり、このタイミングでの離職が集中する傾向があります。
SNSや口コミによる“辞めたくなる空気”の拡散
現代の若手会計士は、SNSで業界内の生の声を簡単にキャッチできます。
X(旧Twitter)や匿名掲示板、転職口コミサイトなどには、「激務すぎて寝れない」「上司ガチャに外れた」などのネガティブな体験談があふれています。
こうした声が“空気感染”的に辞めたい気持ちを強める要因になっており、特に入社1~2年目の不安定な時期に大きな影響を与えています。
実際には一部の過酷な例が拡散されているだけでも、「業界全体がそうなんだ」と思い込んでしまう人が増え、退職の後押しになることもあります。
一時期に辞める人が重なる業界特有の事情
監査法人では、年度末(3月末)や期初(6月)などに退職が集中する傾向があります。これは、監査業務の繁忙期(12月決算~3月末)を終えたタイミングで区切りをつけやすいためです。
このように一斉に数十人単位で退職する法人もあるため、外から見ると「退職者が続出している」と感じやすくなります。
実際には人材流動性の高い業界特性の一部であり、離職率が高すぎる=ブラック企業と決めつけるのは早計です。
このように、監査法人の退職者数が多く見える背景には、若手の理想とのギャップ、SNSの影響、業界の退職タイミングの集中といった構造的な要因があります。
しかし、本当に退職理由として多いのは何なのでしょうか? 次の見出しでは、離職理由TOP3を詳しく解説していきます。
監査法人の離職理由ランキングTOP3

「監査法人は人の出入りが激しい」とよく言われますが、実際にどんな理由で退職を決意する人が多いのでしょうか。ここでは、多くの若手会計士が挙げる離職理由トップ3をもとに整理します。
第3位:年功序列と昇進制度の不透明感
第3位は、「昇進スピードへの不満」です。BIG4では体系的な昇進プロセスがありますが、年次や在籍期間が重視される傾向もあり、努力が正当に評価されにくいと感じる若手が増えています。
また、パートナー昇進までの道のりは長く、実力だけでは突破できない社内政治的な側面もあるため、「将来の見通しが立たない」として転職を検討する人も。特にスタートアップやコンサル業界など、成果主義の環境に魅力を感じる若手層が流出しやすい傾向にあります。
第2位:単調な作業が続くことによる成長実感の薄さ
次に多いのが、「成長している実感が得られない」という理由です。監査業務は企業の財務資料を検証し、整合性を確認する作業が中心。
特に1〜3年目は、エクセルでの数字照合や請求書突合など単調な業務の繰り返しに感じやすい時期です。
「大学まで努力して難関資格を取ったのに、やっているのは単純作業ばかり」というギャップに悩み、自己成長を求めて転職を決断する人も少なくありません。
一方で、これらの基礎業務は将来の監査マネージャーやCFO職で役立つ「会計の土台」でもあるため、短期的な視点だけで辞めるのはもったいないという意見もあります。
第1位:繁忙期の激務とメンタルの限界
最も多いのは、「繁忙期の激務」です。特に上場企業を担当するチームでは、12月決算企業の監査対応が重なる1月〜3月がまさに修羅場。
この時期は朝早くから夜遅くまで働き、平均残業時間が月100時間を超えるケースもあります。上司からのレビュー依頼やクライアント対応、資料差し替えなどが次々に舞い込み、「終わりが見えない」感覚に陥ることもしばしば。
若手のうちは現場でサポート業務が中心となるため、自分の裁量でスケジュールをコントロールできず、心身ともに疲弊してしまう人もいます。結果として、「この働き方を一生続けるのは無理」と判断し、繁忙期明けの春に退職するパターンが目立ちます。
こうして見ると、監査法人の離職理由は「仕事量」「成長実感」「評価制度」の3点に集約されます。
しかし、これらは全ての法人に当てはまるわけではありません。次では、BIG4と中小監査法人での違いを掘り下げていきます。
でもそれって全部の法人に当てはまるの?

「監査法人=辞めたくなる場所」といったイメージが独り歩きしていますが、すべての監査法人が同じ環境ではありません。実際には、法人ごと、部署ごと、チームごとに働き方やカルチャーが大きく異なるのが実情です。この章では、法人規模・チーム文化・ホワイト法人の特徴という3つの視点から、“離職続出”が全体に当てはまるのかを検証していきます。
BIG4と中堅・中小監査法人の違い
まず注目すべきは、BIG4(EY新日本・トーマツ・あずさ・PwC)・準大手監査法人と中小監査法人との違いです。
BIG4や準大手監査法人はクライアント数も職員数も桁違いに多く、繁忙期の業務量が非常に大きい傾向があります。その分、多様な業種・規模の企業に関われる魅力や、英語を使うグローバル案件への関与機会も豊富です。
一方で、中小監査法人では、クライアントとより密な関係が築きやすく、繁忙期の管理も現場裁量が効くため比較的穏やかに進むケースもあるなど、環境が全く異なります。
そのため「BIG4で疲弊したが、中小監査法人に転職して活躍している」という公認会計士も多く見られます。
チーム・上司による働き方の差が大きい現実
同じ監査法人でも、配属チームやマネージャーの方針によって労働環境は大きく異なります。
たとえば、クライアントが上場企業で決算期が集中しているチームではどうしても激務になりがちですし、逆に地方や非上場企業が多いチームでは繁忙期でもバランスの取れた働き方が可能です。
また、上司のマネジメントスタイルも影響が大きく、報連相しやすい雰囲気の中で着実に成長できるチームもあれば、ミスに過敏な文化の中でストレスを感じるケースもあります。
このように、「どこで誰と働くか」が離職理由や働きやすさに直結するのです。
離職率が低い「ホワイト法人」の特徴とは?
一部には離職率が驚くほど低く、定着率の高い監査法人も存在します。そういった法人に共通して見られるのが以下の特徴です:
- オン・オフの切り替えが明確:勤務時間の管理がしっかりしており、長時間労働をよしとしない風土
- 教育とフォロー体制が整っている:新人に対するOJTやレビュー体制が厚く、心理的安全性が高い
- キャリア相談・評価制度の透明性:将来の昇進・異動・転職に関するフィードバックが明確
また、「育児・介護・地方移住」といったライフステージの変化にも柔軟に対応する法人も増えており、長期的に働く意志を支える制度が整備されつつあるのも近年の変化です。
つまり、「監査法人=全てブラック」ではなく、法人選びやチーム選び次第でキャリアの充実度は大きく変わるというのが事実。自分に合った環境を見極めることが、長く働くための第一歩となります。
離職を「ポジティブ」に捉える人たちの共通点

「監査法人=離職者が続出」というイメージが先行する中で、自らの意志で退職を選び、前向きなキャリアを歩んでいる人たちも多く存在します。彼らは単に環境から逃げるのではなく、自身の成長や人生設計に真剣に向き合い、監査法人での経験を次のステップに活かしているのです。ここでは、ポジティブな離職を実現している人たちに共通する思考や行動を掘り下げて紹介します。
キャリアの広がりに目を向けた転職戦略
監査法人を離れる人の中には、「次のキャリアで何を実現したいか」を明確に描いているケースが多く見られます。
例えば、「このまま単調な監査業務を続けるよりも、より事業に近い立場で成長したい」という動機から、事業会社の経理・経営企画部門に移る人もいます。また、「専門性をもっと活かして、コンサルタントやFAS業務に挑戦したい」と考え、転職を決断する人もいます。
このように、ただ「辞めたいから辞める」のではなく、「次にやりたいことがあるから辞める」というスタンスが、結果として前向きな離職につながっています。
キャリア戦略を描く上で、以下のようなアクションを取っている人が多いのも特徴です:
- 自己分析を通じて「自分の得意・苦手」「価値観」「理想の働き方」を把握
- 転職エージェントやロールモデルとの対話で、業界研究・職種研究を深める
- 現職のうちから副業や社外活動を通じて視野を広げる
このように、計画的かつポジティブに「卒業」を選ぶことが、転職後の活躍につながっているのです。
監査経験が活きる業界:FAS・経理・コンサル・スタートアップ
監査法人での経験は、思っている以上に多くのフィールドで活かすことができます。実際に退職後の進路として多いのは、以下のような業界・職種です。
FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)
M&Aや企業再生などの高難度で高収入な専門業務に携わることができます。監査業務で培った財務諸表の読解力や論理的思考力が、FASでは大きな武器になります。BIG4出身者はFAS部門への異動や転職が多く、ステップアップの王道とされています。
経理・経営企画(事業会社)
事業会社においてCFOや経営層に近いポジションで活躍したい人には、経理や経営企画が人気です。監査法人出身者は「経理の守備力」に加え、ガバナンスや内部統制の観点も身についており、信頼されやすい即戦力人材と評価されます。
コンサルティングファーム
業務改善・リスク管理・システム導入などを扱うコンサル業界も、監査出身者の転職先として定番です。資料作成能力・ロジカルシンキング・コミュニケーション力など、監査現場で鍛えられたスキルが、そのまま活きるケースが多いです。
スタートアップ・ベンチャー
成長意欲の高い人は、経理・財務のプロ人材としてスタートアップに転職し、CFO候補として活躍することもあります。監査法人では味わえなかったスピード感や裁量、経営への関与を求めて、チャレンジする人が増えています。
このように、監査法人での実務経験はキャリア市場での価値が高いため、辞めることを悲観する必要はまったくないのです。
「辞める=失敗」ではない時代の価値観
ひと昔前までは、「新卒で入った会社をすぐ辞めるのは根性がない」という価値観が根強く存在していました。しかし、今や若手の離職や転職はごく当たり前のこと。特に監査法人のように明確なスキルが身につく職場であれば、数年で卒業するのは自然な流れとも言えます。
さらに、以下のような時代背景もあります:
- 転職市場の拡大により「辞めてからでもやり直せる」柔軟なキャリア形成が可能に
- リモートワークや副業など、多様な働き方が社会に浸透
- 若手の価値観として「やりがい」や「自分らしさ」を大切にする傾向が強い
こうした背景の中で、「キャリアを柔軟にデザインできる時代」に生きる私たちにとって、「退職=敗北」という見方はもはや過去のものです。
むしろ、自分のキャリアを主体的に選び取る力こそが、これからの時代に求められる重要なスキルです。
「辞めた人=失敗した人」というレッテルは、もはや古い常識です。むしろ、自分の価値観と向き合い、次のステップに踏み出した人こそが、柔軟でたくましいキャリアを築いています。
監査法人というフィールドで培ったスキルや人脈は、あなたの武器になります。「辞めること」自体を目的にせず、「その先に何を目指すか」を見据えることが、ポジティブな離職のカギなのです。
監査法人で働き続けることのメリット

退職者が続出するという話を聞くと、不安になるかもしれません。しかし一方で、監査法人に長く勤めることにも大きなメリットがあります。辞めるべきか残るべきか悩んでいる人にとって、働き続けることの価値を知っておくことはとても重要です。
安定した給与水準と福利厚生の充実
監査法人は、他の業種と比較しても安定した収入と手厚い福利厚生が整っている点が大きな魅力です。特にBIG4においては、以下のようなメリットがあります。
- 若いうちから年収600〜700万円以上を狙える給与テーブル
- 完全週休二日制・年間休日120日以上など、働き方の制度が整っている
- リモートワーク制度やフレックスタイム制度など柔軟な勤務体制も拡大中
- 資格取得支援、自己研鑽費補助など成長支援制度が豊富
給与水準だけでなく、安定した環境で働けることは、将来設計や家族との生活を見据える上でも大きな安心材料となります。
キャリアの土台としての「圧倒的な信頼性」
監査法人でのキャリアは、他業種に転職する際のブランド力として非常に強力です。特に監査法人で長く働き、マネージャーやシニアマネージャーにまで昇進した人は、以下のような評価を得やすくなります。
- 上場企業とのやりとり、内部統制対応、会計基準対応などの高度な経験
- リーダーとしてプロジェクトを推進したマネジメント力
- 顧客対応や部下育成の中で身につく対人スキルやリーダーシップ
「監査法人で長くやってきた=一通りのビジネススキルがある」という評価は、転職市場でも強い武器になります。
将来的なパートナー昇格の可能性と経営参加
監査法人では、シニアマネージャー以降にパートナー昇格の道が開かれています。これは単なる昇格にとどまらず、法人経営の意思決定にも関わる重要なポジションです。
- 年収1,500万〜3,000万円以上の高収入も夢ではない
- 経営層として事業戦略や人材育成に深く関われる
- クライアントに対しても「法人の顔」として信頼される存在になれる
このように、監査法人で長期的にキャリアを積み上げていくことで、公認会計士としての専門性を磨きながら、経営者的な視点も身につけることが可能です。
離職が目立つ一方で、監査法人に残って活躍する人も多数います。安定した給与・制度、キャリアの信頼性、パートナー昇格といった長期的メリットを理解し、自分の目指すキャリアと照らし合わせて判断することが重要です。辞める/辞めないはどちらが正解というものではなく、自分にとってのベストな選択かどうかが問われているのです。
まとめ:離職が多いのは事実、それでも選ぶ価値がある監査法人

「監査法人 退職者 続出」という言葉を聞くと、不安を感じる人も多いでしょう。しかし、離職者が多い背景には、繁忙期のハードワークやキャリアの選択肢が豊富であることが関係しています。つまり、ネガティブな要因だけでなく、「他にも選択肢があるからこそ離職する人もいる」という側面もあるのです。
一方で、監査法人でのキャリアには、高収入・高信頼の専門職としてのポジション、経営層への昇格チャンス、そしてキャリアの基盤としての強さといった魅力もあります。働き続けることで見えてくる景色も確かに存在します。
この記事を読んだあなたには、単に「辞めるべきかどうか」ではなく、自分のキャリアビジョンに照らして判断する視点を持ってほしいと思います。退職者が多いという事実だけに左右されず、自分にとってのベストな道を選びましょう。