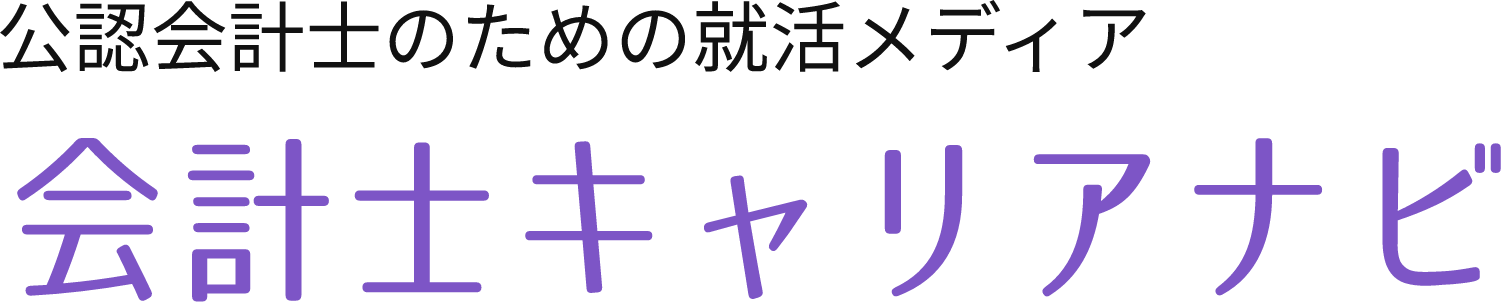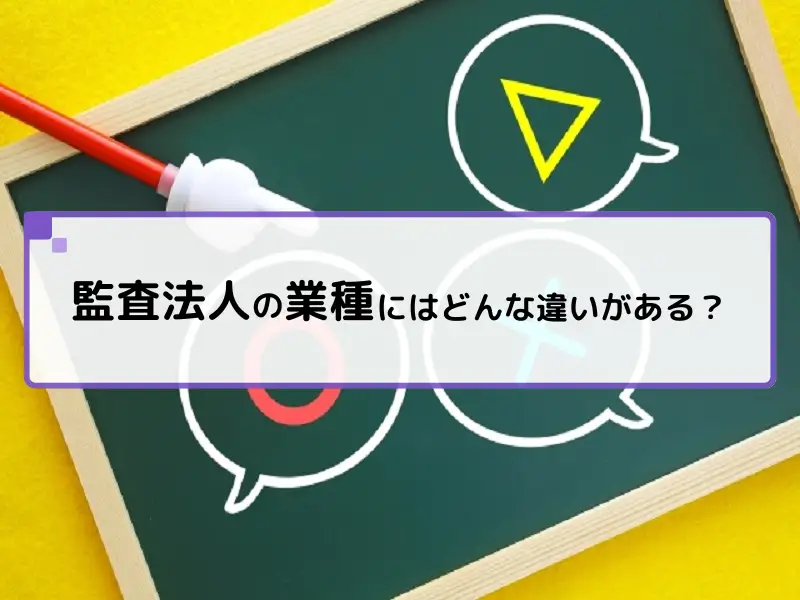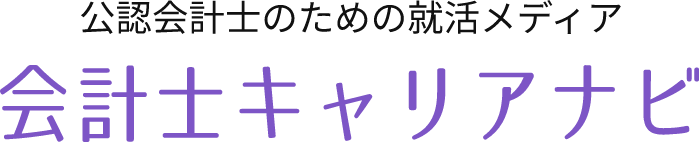「監査法人で担当する業種ってどう違うの?どの業界に配属されると自分に合っているのか不安…」
公認会計士試験が終わり、いざ監査法人への就職を考えたとき、多くの就活生がぶつかるのが「配属される業種によって仕事の内容はどう変わるのか?」という疑問です。金融や製造、IT、サービス業など、多様な業界の被監査会社を抱える監査法人では、業種ごとに必要な知識や業務の進め方に大きな違いがあります。
本記事では、監査法人で関われる業種の一覧を紹介し、それぞれの魅力や特徴、必要なスキルの違いを詳しく解説します。 これにより、あなたがどんな業種に向いているのか、将来どのようなキャリアにつながるのかをイメージしやすくなるでしょう。
就職先を選ぶうえで、「業種」は意外と見落とされがちですが、長期的なキャリアの充実度を左右する重要な要素です。ぜひ本文を通じて、自分に合った未来の姿を描くヒントを掴んでください。
監査法人が担当する主な業種とは?

監査法人に就職する際、多くの就活生が気になるのが「どんな業種の会社を担当するのか」です。実は、監査法人は非常に幅広い業界を対象に監査業務を行っており、それぞれの業種ごとに求められる知識や対応も異なります。ここでは、公認会計士が携わることの多い主要な業種について解説します。
金融業界(銀行・保険・証券)との関わり
金融業界は監査法人が最も注力する業界の一つです。特に都市銀行、地方銀行、大手証券会社、保険会社などが対象となります。
- 金融商品やデリバティブなどの複雑な会計処理に対する監査が必要
- 金融庁への報告義務など、制度面での対応が厳密
- リスク管理や内部統制の検証が重要
この分野を担当することで、金融会計に強くなり、将来的に金融業界への転職や専門アドバイザリー業務にも展開しやすくなります。
製造業やインフラ系の監査の特徴
製造業は日本の基幹産業であり、多くの上場企業が存在します。電機、機械、自動車、化学などの業種に加え、電力・ガス・通信といったインフラ系企業も数多くあります。
- 在庫評価や減損会計の知識が求められる
- 海外子会社の監査や連結決算対応も多い
- 固定資産会計や収益認識基準の検討がポイント
これらの業界では、グローバルな監査対応力が磨かれます。
IT・ベンチャー企業に対する監査業務
スタートアップやテック企業への監査は、近年急速に増加しています。これらの企業では、会計処理が特殊であったり、スピード感のある経営が特徴です。
- 未上場企業のIPO支援に関与できる機会あり
- 様々なストックオプション制度の採用も多い
- 会計以外にビジネスモデルや業績評価の知見も必要
こうした企業を担当することで、将来的にベンチャー投資やCFO候補へのキャリアパスも見えてきます。
業種によって監査のスタイルは大きく変わります。次は、業種ごとにどのような監査手続が求められるのかを見ていきましょう。
業種ごとに異なる監査のスタイル

監査業務はすべて一様に行われるわけではなく、業種によってその進め方や重点項目は大きく異なります。ここでは、業種ごとに求められる知識や監査手続の特徴、さらに大手監査法人、準大手監査法人、中小監査法人での違いについて紹介します。
監査手続における業界特有のポイント
業界ごとにビジネスモデルが異なるため、それに応じた監査手続も必要です。
- 製造業:在庫評価、原価計算、棚卸立会が必須
- 金融業:自己査定、金融商品取引、デリバティブ取引の妥当性の検証
- 不動産業:減損処理やプロジェクト進行基準、資産評価が中心
- IT・ベンチャー:無形資産、収益認識、ストックオプションの処理
こうした手続きは、業種の特性に合った形で実施されるため、会計基準の理解だけでなく業界知識が不可欠です。
業種別に求められる知識と対応力
担当する業種によって、次のような知識やスキルが求められます。
- 製造業・インフラ系:設備投資・減価償却・原価計算に強いと◎
- 金融系:経済動向や金融商品に関する理解力が重要
- IT業界:SaaSモデルやサブスクリプション会計、無形資産への知識が武器に
これらの知識は監査の正確性と効率性を高める鍵となり、将来のキャリアにおいても大きなアドバンテージになります。
大手、準大手監査法人、中小監査法人での業種別担当傾向
入所する監査法人の規模によって、担当する業種にも傾向があります。
- BIG4などの大手監査法人:
- 大企業の監査が中心
- 業種は固定されやすく、深掘り型のキャリア
- 金融・インフラ系など高難度業界が多い
- 準大手監査法人:
- 成長段階のミドルクラス企業の監査が中心
- 業種に縛られず幅広いクライアントの監査が可能
- 上場企業とIPO準備企業の監査を同時に経験可能
- 中小監査法人:
- 幅広い業種の被監査会社に対応
- 一人あたりの担当範囲が広く、多角的なスキルが身につく
- ベンチャーや地域密着型企業が多い
どの監査法人に就職するかによって、経験できる業種やキャリアの方向性が変わるのです。
次は、こうした業種経験が将来のキャリアにどう影響するかについて見ていきましょう。
業種によって変わるキャリアの広がり

監査業務を通じて得られる経験は、将来のキャリアに大きな影響を与えます。担当する業種によって、その後のキャリアパスの方向性や活躍の場が変わってくることを理解しておきましょう。
特定業界に特化することのメリット
特定の業種に継続して関わることで、専門性が高まります。以下のような利点があります。
- 深い業界知識の蓄積:金融や不動産など、会計処理の複雑な業界では特に重宝される
- 企業内経理や経営企画職への転職で有利
- 業界横断のアドバイザリー業務への道が開ける
たとえば金融業界での経験を積んだ会計士は、銀行や証券会社の内部監査やコンプライアンス部門への転職で優位に立てます。専門性はキャリア形成の強力な武器になります。
ジェネラリストとしてのキャリア形成
一方で、複数業種を経験することで得られる「汎用性」も見逃せません。
- 幅広い会計処理に精通できる
- 経理・財務職への転職で即戦力になれる
- コンサル業界など、複合的な視点を求められる職種にマッチ
特に中小監査法人では、多様な業種を短期間で経験することができ、若手のうちから複数のスキルを並行して磨ける環境があります。
監査法人で得た知見の転職先への応用
監査法人で得た経験は、転職市場でも高く評価されます。
- 製造業の監査経験 → 経理部門での在庫管理や原価計算
- ITベンチャーの監査経験 → スタートアップのCFOやIPO準備室への転職
- 金融業界の監査経験 → リスク管理・投資分析部門へのシフト
このように、担当した業種はそのまま転職後の武器になるのです。特に業界ごとの専門用語や商習慣に精通している点は、実務で即戦力とみなされる要因になります。
次は、実際に20代の若手会計士がどのような業種に関わっているのか、その傾向と事例を見ていきましょう。
若手会計士が携わる業種の実例

実際に監査法人に入所した若手会計士たちが、どのような業種を担当しているのか気になる方も多いでしょう。配属先やプロジェクトによって経験する業界は様々であり、それがその後のキャリアにも影響を与えます。
20代が関わるチームと担当業種の傾向
若手会計士が初めに配属されるのは、比較的業務量の多い業種や人手が必要なチームであることが一般的です。
- 製造業・小売業などの中堅企業の監査チーム
- ITベンチャーやスタートアップの監査業務(特にIPO準備案件)
- 公益法人や学校法人など、公共性の高い団体の監査
これらの業種は、学べることが多いため、若手の成長機会として選ばれることが多いです。特にIPO準備中のベンチャー企業では、会計の特殊性に加え、成長スピードの速さを間近で体感できます。
初期配属によるキャリアへの影響
最初に配属される業種は、将来的な専門性やキャリアの方向性に少なからず影響を与えます。
- 金融業界に配属された場合:リスク管理や複雑な金融商品への理解が深まり、金融コンサルや内部監査への道が開ける
- 製造業に配属された場合:在庫管理や原価計算のスキルを習得し、経理や経営企画に強い人材となれる
- ベンチャー系配属の場合:変化への柔軟性やITリテラシーが身につき、CFO候補としての資質が磨かれる
このように、最初の数年でどの業界の監査に携わるかは、自分の市場価値を左右する重要な要素です。
配属希望の出し方と業種の選び方
監査法人によっては、配属先の希望を事前に提出する機会があります。希望の業種に配属されるためには、以下のような工夫が効果的です。
- 面接や研修中に関心業界を明確に伝える
- 大学時代の研究テーマやインターン経験を関連付けてアピールする
- 語学やITスキルなど、特定業種に活かせるスキルを示す
ただし、希望が通るとは限らないため、配属された業種でまずは力をつける姿勢も重要です。どの業界にも学ぶべきことは多く、それが結果的に次のチャンスを広げてくれます。
次は、キャリアに迷っている就活生こそ監査法人で多様な業種に触れるべき理由を紹介します。多くの業界を経験できる監査法人の魅力を見ていきましょう。
迷うならまずは監査法人で業種の幅を知ろう

業種選びに迷うのは、就活生にとって自然なことです。しかし、実際に働き始める前にその業界の中身を知るのは難しいもの。だからこそ、公認会計士試験が終わり、就職先に悩んでいるあなたにとって、監査法人はさまざまな業界に触れる絶好のステージとなります。
多様な業界に触れられる監査法人の強み
監査法人では、1人の会計士が複数の被監査会社を担当することが一般的です。そのため、短期間で様々な業種に触れることができます。
- 製造業・小売業・金融業など、多岐にわたる被監査会社先
- 上場企業から中小企業、公益法人まで多様な規模
- 業界ごとに異なる会計処理・業務プロセスを学べる
このような環境では、自分に合った業界や興味を持てる分野が自然と見えてきます。最初から「この業界に行きたい」と決め打ちする必要はありません。
将来の専門性につながる業界選び
複数業界を経験する中で、「もっと深く知りたい」と思える業種に出会うことがあります。監査法人では、その希望をもとに担当業種を変えていくことも可能です。
- 例1:ITベンチャーに魅力を感じ、将来はCFOとしてジョインしたい
- 例2:医療法人のガバナンス強化に関心を持ち、ヘルスケア特化のコンサルへ転職
- 例3:不動産業界の会計に強みを持ち、REIT運用会社へステップアップ
このように、実務経験を通じて“興味”を“専門性”に変えることができるのは、監査法人ならではの魅力です。
業種を知ることで広がるキャリアの可能性
どの業界も実際に働くまでは、そのリアルが見えにくいものです。監査業務を通じてその企業の組織構造、収益モデル、文化、業界全体のトレンドに至るまでを理解できます。これは将来のキャリアを考える上で大きなアドバンテージです。
- 「この業界は合わない」と気づける機会にもなる
- 複数業種に精通することでジェネラリストとして活躍できる
- 業界横断の知見が、経営コンサルや戦略職への布石にも
つまり、監査法人は“業界研究”を仕事として実践できる環境です。迷いのある就活生にとって、最もリスクが低く、将来のキャリア選択の幅を広げるファーストキャリアと言えるでしょう。
まとめ

この記事を通じて、監査法人が関わるさまざまな業種の種類や特徴、監査手法の違い、キャリアの広がりを見てきました。あなた自身が「どんな業界に向いているのか」「将来どんなキャリアを描きたいのか」について、少しずつイメージが湧いてきたのではないでしょうか。
もしもあなたが今、業種選びに迷っているなら——。その迷いを無理に今すぐ断ち切る必要はありません。むしろ監査法人というフィールドで、多様な業界に“触れてから選ぶ”という選択肢も大いにアリなのです。
監査法人での仕事は単なる帳簿のチェックに留まりません。その業界のビジネス構造や課題、成長の兆しを最前線で見ることができる貴重なポジションです。そして、その経験は将来の転職や独立、専門領域の確立に大きな価値をもたらします。
特に、20代でキャリアをスタートさせるあなたにとっては、
- 自分の“得意”や“関心”を実務を通して見つける
- 特定業界に深く入り込む前に比較対象を持つ
- 様々な業界から必要とされるスキルを磨く
といったメリットが満載です。
最後に、「迷うならまずは監査法人へ」という言葉をもう一度贈ります。将来、どの業界で活躍するにしても、まずは複数の業界を客観的かつ専門的な立場で知ることができる監査法人の経験は、かけがえのない土台になるでしょう。
あなたのキャリアの第一歩が、自信と可能性に満ちたものとなることを心より願っています。