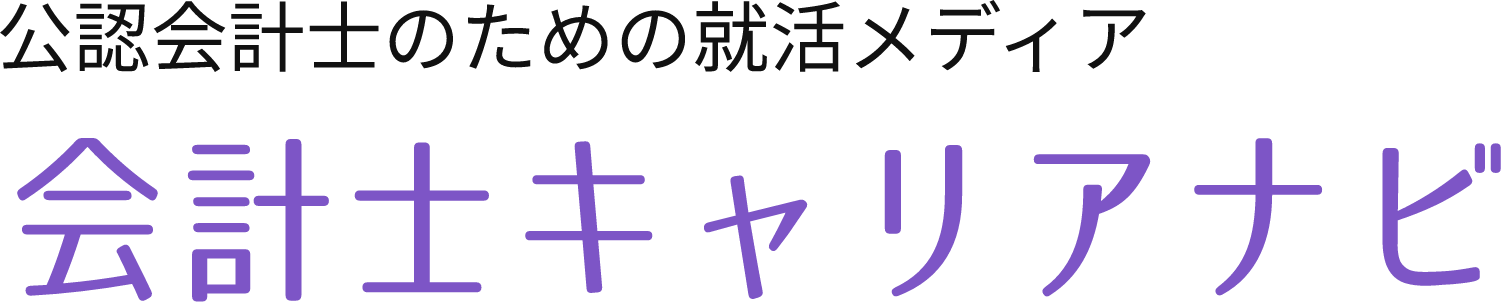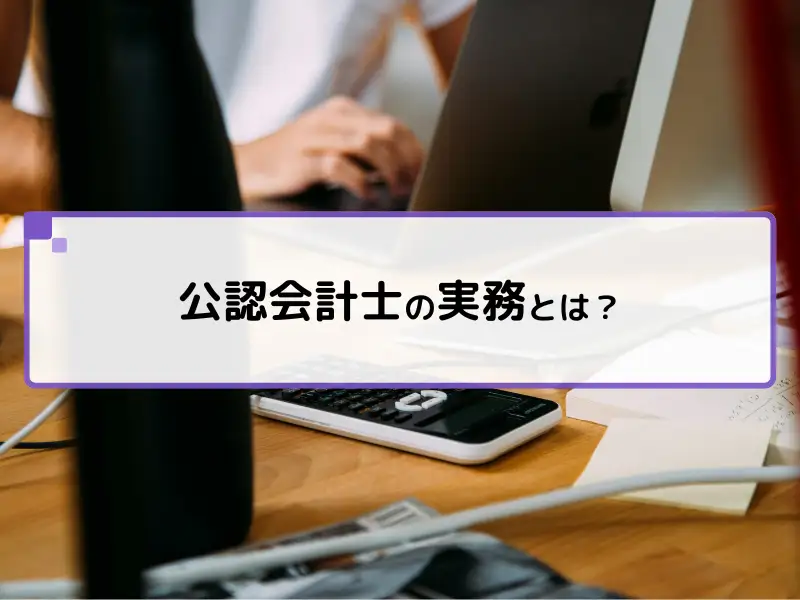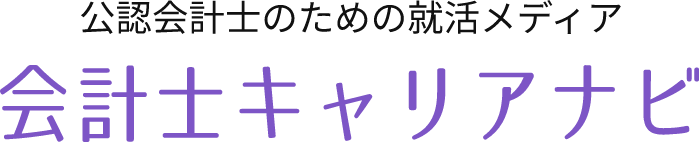「公認会計士に合格したのはいいけれど、実務って実際どんなことをするんだろう?」
そう感じている方も多いのではないでしょうか。特に、監査法人への就職を考えている就活生にとって、試験勉強と実務の違い、現場で求められる役割、1年目の働き方は大きな関心事だと思います。
本記事では、公認会計士の実務について、仕事内容や1日の流れ、補習制度との関係、現場で直面するギャップまでを体系的に解説します。
読み終えるころには「入社前に知っておいてよかった!」と思える実践的な知識が身についているはずです。
それでは、公認会計士としての第一歩を踏み出すための実務の世界を一緒に見ていきましょう。
目次
公認会計士の実務とは?役割と価値を理解しよう

試験に合格した今、次に立ちはだかるのが「実務」という壁。では、公認会計士としての実務とは具体的に何を指すのでしょうか?ここでは、試験勉強では見えてこなかった“リアルな仕事”の中身と、その社会的価値について整理していきます。
公認会計士の主な仕事内容とは
公認会計士の実務は主に3つに分けられます。
1つ目は財務諸表監査。これは監査法人で働く会計士の中核業務であり、企業の財務諸表が正確に作成されているかを第三者の立場からチェックします。2つ目はアドバイザリー業務で、M&A支援や内部統制構築支援など、企業の課題解決に貢献する仕事です。3つ目は税務支援で、税理士業務に近いポジションで法人や個人の税務申告や相談に応じるケースもあります。
これらの業務は、単に数字を追うだけでなく、「会計のプロ」としての判断力や倫理観が問われる責任の重い仕事です。
なぜ公認会計士の実務が重要とされるのか
実務の意義は、社会から求められる「信頼」に直結しています。たとえば、投資家や株主、金融機関は、企業の財務諸表を信頼して意思決定を行っています。その信頼の裏付けが、会計士による監査です。
また、実務を通して養われるのは、机上の知識では補えない「現場力」です。現場でしか得られない経験を積むことで、判断の引き出しが増え、応用力が身につきます。会計士が“会計の専門家”として名乗れるのは、こうした実務経験を経てこそ。だからこそ、試験合格はあくまでスタート地点にすぎないのです。
試験合格後に待っている「実務」の現実
合格後、多くの人が監査法人へ入社しますが、待っているのは慣れない用語、スピード感、複数人での共同作業といった“非・試験的世界”。たとえば、試験で学んだ「財務諸表の見方」と、実際の現場で使用される被監査会社の会計システムや監査調書の扱いには大きなギャップがあります。
また、先輩会計士や被監査会社とのやりとりも多く、コミュニケーション能力が試される場面が頻繁に訪れます。中には「思っていたより地味で大変」と感じる人も少なくありませんが、それでも一歩ずつ積み重ねることが成長への鍵です。
監査法人での1年目の仕事と1日の流れ

試験に合格したあと、多くの会計士は監査法人に入社し、いよいよ“実務家”としての第一歩を踏み出します。ここでは、1年目に経験する仕事の内容や、日々のスケジュール、チーム内での立ち位置について、できるだけリアルにお伝えします。
初年度に任される代表的な業務
入社直後の1年目に任される業務は、基本的には「サポート業務」が中心です。たとえば以下のような仕事があります:
- エビデンスの取得:監査対象となる証憑(請求書や契約書など)を集める業務。
- 数値の突合:会計帳簿と証憑との整合性を確認する作業。
- 監査調書の作成:上司の指示のもと、調書(監査記録)を作成します。
一見すると地味な作業が多く感じるかもしれませんが、これらの業務を通して「監査とは何か」「どう判断するか」といった根本的な感覚が身についていきます。
監査チームの中での立ち位置
監査は必ずチームで行います。典型的な構成は以下の通りです:
- パートナー(署名者):監査の責任者。
- マネージャー:監査の全体進行を管理。
- シニアスタッフ:現場での実務リーダー。
- スタッフ(あなた):主に実務の実行担当。
新入社員はこの中で、スタッフとして配置されます。現場では、主にシニアスタッフの指示を受けながら作業を進めていきますが、積極的に質問し、自ら理解を深める姿勢がとても大切です。コミュニケーション能力もこの時点で大きく育ちます。
忙しい時期の1日のスケジュール例
監査法人には“繁忙期”が存在します。特に3月決算の企業が多い日本では、1月〜5月が最も忙しい時期です。その時期の1日のスケジュール例を見てみましょう:
| 時間帯 | スケジュール例 |
|---|---|
| 9:00 | 出社、朝会、今日のタスク確認 |
| 9:30 | 被監査会社の資料チェック、監査調書作成 |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | チームミーティング、進捗共有 |
| 14:00 | 被監査会社とやりとり(メールや訪問) |
| 16:00 | 上司への報告・修正 |
| 18:00〜19:30 | 残タスクの処理、退勤(※繁忙期は残業あり) |
このように、1日中パソコンに向かって作業する日もあれば、被監査会社先に出向いて対応する日もあります。数字だけでなく、人とのやりとりが増えることに驚く人も多いでしょう。
被監査会社対応で求められるスキルとは?

「会計士=数字に強い人」というイメージを持つ方は多いかもしれません。しかし、監査の現場では、「人と向き合う力」も非常に重要です。被監査会社対応は、監査業務の中でも欠かせない要素であり、特に若手のうちから意識して身につけておくべきスキルがいくつもあります。
監査における「被監査会社対応」とは何か?
監査法人の業務では、企業の経理・財務部門とやり取りをしながら、資料の提供を依頼したり、処理内容の確認を行ったりします。
この一連のやりとりが「被監査会社対応」と呼ばれています。
例えば以下のような場面があります:
- 決算書に関する会計処理の意図を確認
- 必要なエビデンス(証憑)の依頼
- 提出資料の不備や矛盾点の指摘と調整
これらの場面では、単に事務的に依頼するだけでなく、「なぜその資料が必要なのか」「どのように修正すべきか」をわかりやすく説明する力が必要です。
初学者が身につけたいコミュニケーション能力
新入職員の立場でも、被監査会社と接点を持つ機会は多くあります。特に以下のような能力が求められます。
- 報連相の徹底 上司への報告・連絡・相談を怠らないことは大前提。被監査会社とのやりとりも、必ずチームで共有します。
- 聞き上手になる力 相手の話を遮らず、丁寧に耳を傾ける姿勢が信頼感を生みます。初対面の相手とも円滑に話す力が問われます。
- 言葉を噛み砕くスキル 専門用語を使わずに伝える力は、特に重要です。経理担当者といっても、全員が会計士と同じレベルの知識を持っているわけではありません。
監査法人での被監査会社対応は「交渉」ではなく「協力」です。敵対的な関係ではなく、正しい決算を一緒につくりあげる“パートナー”としての姿勢が必要です。
失敗から学ぶ、被監査会社対応のリアル
1年目は、緊張してうまく話せなかったり、メールでの表現が冷たく感じられたりすることもあります。例えば、
- 「資料を至急提出してください」とだけ書いてしまい、相手の気分を害してしまった
- 経理担当者に質問しても要領を得ず、別の部署に聞く必要が出たが、手順を誤ってトラブルに
このような経験は誰もが通る道です。失敗しても、チームのフォローがありますし、「なぜうまくいかなかったのか」を振り返る姿勢があれば、確実に成長していきます。
繁忙期のスケジュールと働き方の実態

「監査法人は忙しい」という話を聞いたことがあるかもしれません。
特に3月決算企業を多く抱える日本では、1月〜5月がいわゆる“繁忙期”です。この時期、会計士たちはどのようなスケジュールで働いているのでしょうか?ここでは、実際のスケジュール例や働き方の工夫について解説します。
繁忙期の1日の流れ
繁忙期のある1日を例に取ると、以下のようなスケジュールになることが一般的です。
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 9:30 | 出社/被監査会社訪問開始(直行の場合も) |
| 10:00 | チーム朝会・業務の割り振り |
| 11:00 | エビデンス(証憑)チェック、資料のレビュー |
| 13:00 | 昼休憩(タイミングは柔軟) |
| 14:00 | 経理部門と会計処理の内容確認・質問対応 |
| 17:00 | チームミーティング・進捗報告 |
| 18:00〜21:00 | 引き続き調書作成・レビュー対応など |
| 21:30頃 | 退勤(時期・繁忙度によって変動) |
もちろん、日によって波はありますが、20時〜21時退勤がデフォルトになりやすいのが繁忙期の特徴です。
土日出勤や残業は当たり前?
繁忙期には土曜日出勤や深夜残業も発生します。ただし、全員が毎週出勤するわけではなく、チーム内で調整したり、法人によっては“振替休日”を必ず取得するルールもあります。
また、以下のような工夫がされているケースも増えています。
- 時差勤務制度の導入(朝早く来て早く帰る)
- リモートワーク活用(在宅での調書作成)
- 補助者を増員して業務を分担
こうした制度が整っている法人では、「働きやすさ」と「やりがい」のバランスが取れています。
若手が知っておくべき“メンタルの守り方”
繁忙期に最も消耗するのは、実は“気持ち”の面かもしれません。
- ミスが続いて自信を失う
- 疲労で判断力が鈍る
- チーム内でのコミュニケーションが減る
こういった状況に陥らないためには、「わからないことは早めに聞く」「雑談や息抜きを大切にする」といった工夫が欠かせません。
新人のうちは「完璧にこなさなきゃ」と思いがちですが、実務は“チーム戦”です。先輩や上司も過去に同じ失敗をしてきています。自分を追い詰めすぎないことが、長く会計士を続けるための秘訣です。
会計士の実務を通じて得られるスキルとキャリアの広がり

公認会計士として実務に就くことで、ただ単に「監査ができるようになる」だけではありません。
むしろ、実務経験こそがあなたのキャリアの選択肢を大きく広げる武器となります。
ここでは、会計士の実務を通じて得られるスキルや、そこからどういったキャリアパスが拓けるのかを紹介します。
実務で身につくスキルとは?
監査法人での実務経験は、多様なスキルを自然と身につけることができます。特に以下のような力が磨かれます。
- 会計・監査知識の実践的応用力 学んだ理論を「現場」で活用しながら、実践を通じて深める力。IFRS、J-GAAPの理解も進みます。
- 論理的思考力と説明力 監査手続の妥当性を社内・被監査会社双方に説明する必要があるため、筋道立てた話し方が求められます。
- プロジェクト管理スキル 期限が明確な監査業務の中で、業務の優先順位を自分で決め、段取りを組む力が養われます。
- チームでのコミュニケーション能力 会計士は“個人プレー”ではなく、チームで動く職種。密なコミュニケーションが成功のカギを握ります。
これらは、監査法人に限らず、あらゆるビジネス現場で重宝される汎用スキルです。
実務経験がキャリアにどうつながる?
監査法人で2~5年働くと、以下のような多様なキャリアパスが視野に入ってきます。
- コンサルティング会社への転職 M&A、財務デューデリジェンス、内部統制支援などへ。FASやBIG4のアドバイザリー部門などが定番。
- 一般事業会社の経理・財務部門へ 上場企業の決算担当や、CFO候補としてキャリアを積む人も。
- ベンチャー企業の管理部門立ち上げ 会計知識だけでなく、仕組み構築力も期待され、スタートアップから声がかかることもあります。
- 独立開業(税理士法人や会計事務所) 実務経験後、税理士資格を追加取得し、独立する会計士も増えています。
実務で積んだ経験が、「自分にしかできない仕事」への入り口になるのです。
若手会計士がキャリアを広げるためのポイント
実務を“消化試合”にせず、キャリアにつなげるためには以下のような姿勢が重要です。
- 「なぜこの手続が必要か」を意識して動く 表面的にタスクをこなすのではなく、常に「目的」を考えることで、成長の速度が変わります。
- 被監査会社の業務や業界への興味を持つ 特定業界に詳しくなることで、その後の転職先や専門分野にもつながります。
- 自分の“得意”を見つけて伸ばす IT監査、IPO支援、内部統制など、どこかで“尖る”ことで市場価値が高まります。
公認会計士の実務理解はキャリアの第一歩

この記事を読むことで、「公認会計士の実務とは何か?」という疑問は解消されましたか?
もし、冒頭で抱えていた「どんな仕事をするのか」「どんな力がつくのか」「その先に何があるのか」といった不安や疑問が、少しでもクリアになっていれば幸いです。
今回の記事では、公認会計士の代表的な実務である監査業務の概要から1日の仕事の流れ、必要なスキル、配属の仕組み、そして実務経験を通じて得られるキャリアの広がりまで、体系的に解説しました。
公認会計士の実務は一見すると地味に思えるかもしれませんが、その中には高度な知識と判断力、対人スキルが問われるプロフェッショナルな世界があります。
そしてその経験は、将来の転職や独立、さらには経営層への道にまでつながる大きな資産になります。
この記事を読んで、「実務のリアル」が少しでも明確になり、「監査法人で働く自分」をより鮮明にイメージできたなら、ぜひ次の一歩を踏み出してみてください。
あなたのキャリアは、実務経験を通じて確実に広がっていきます。