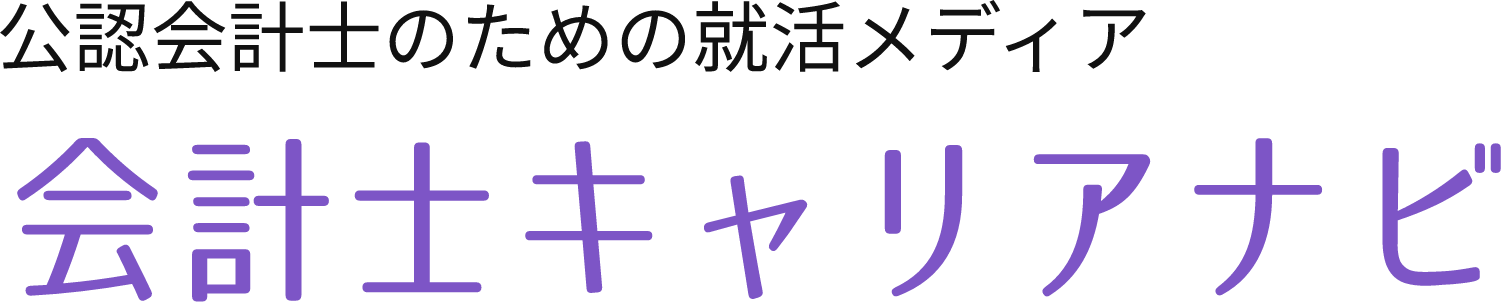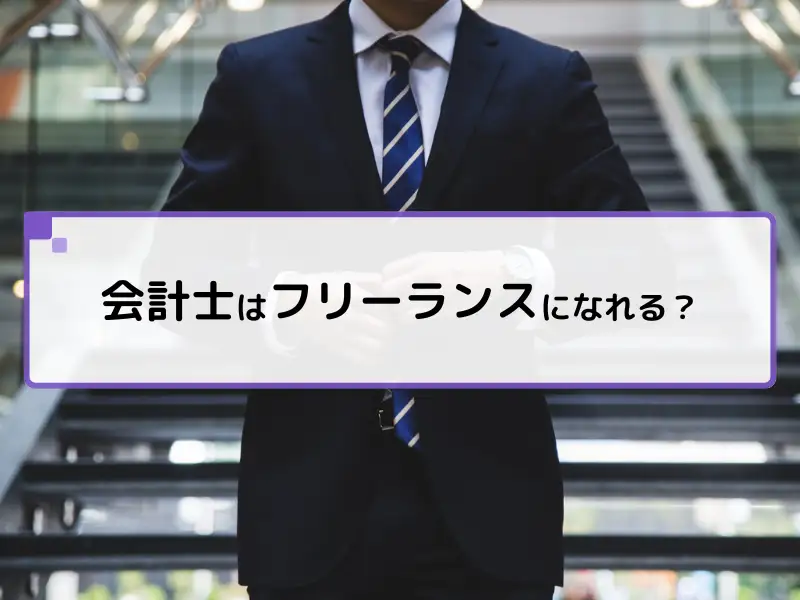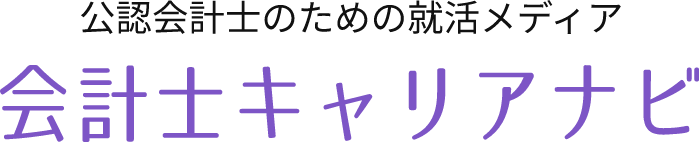「フリーランスの会計士って、実際どんな働き方をしているの?」
「監査法人を辞めて独立してもやっていけるの?」
「そもそも、フリーランスになるには監査法人を経験すべきなの?」
公認会計士としてキャリアの第一歩を踏み出す際、多くの人がまず選ぶのが「監査法人」。BIG4や中堅監査法人といった組織は、試験合格者にとっての“王道ルート”であり、安定した環境と専門性の高い業務を通じて、会計士としての土台を築くことができます。
一方、近年注目を集めているのが「フリーランス会計士」という新たなキャリアの選択肢です。企業に属さず、自らのスキルと信頼を武器に独立し、税務・会計・経営支援など多様な領域で活躍する会計士が増えてきています。特にコロナ禍以降、柔軟な働き方を求める流れが強まり、ライフスタイルや価値観に合わせて独立を目指す若手会計士も珍しくありません。
では、監査法人からフリーランスになるというキャリアルートは、果たして本当に“王道”と言えるのでしょうか?
この記事では、以下のポイントを通じて、あなたの疑問に答えていきます。
- フリーランス会計士が増えている背景とその魅力
- 監査法人で得られるスキルや信頼が、なぜ独立後に武器になるのか
- 実際に独立してからの仕事内容や年収のリアル
- いつ辞めるべきか、転身のタイミングをどう判断するか
- フリーランスを見据えて監査法人で「何を経験すべきか」
この記事を読むことで、「とりあえず監査法人に入る」ではなく、「監査法人で何を得て、どう活かすか」という戦略的なキャリア観を持てるようになります。
就職活動中の今、少しでも「フリーランスもアリかも」と感じているあなたへ。この記事は、そんな“選択肢の1つ”を、現実的かつ戦略的に考えるための材料になります。
次のセクションからは、なぜ今「監査法人→フリーランス」という道が注目されているのか、その理由を深掘りしていきましょう。
目次
なぜ多くの会計士がフリーランスを目指すのか?

監査法人という安定ルートがあるにもかかわらず、近年は若手会計士の間で「独立したい」「フリーランスでもっと自由に働きたい」という声が増えています。その背景をひも解くと、働き方の価値観が“安定より裁量”へシフトしていることが見えてきます。
自由な働き方と収入の可能性
- 働く時間・場所を自分で決められる(リモート案件も拡大)
- 案件単価を自ら交渉でき、実力次第で年収1,000万円超えも狙える
- 税務・経営支援・財務コンサルなど専門分野ごとに高付加価値化が可能
専門性を活かした独立のしやすさ
- 公認会計士は「信用」が強み ⇒ 開業届・契約締結のハードルが低い
- 税務署・金融機関・VCからの紹介が得やすく、案件を継続的に確保
- 法定監査・IPO支援などニッチ領域で競争が少ない
ライフスタイル重視のキャリア志向
- 長時間労働のピークを避け、プライベートと仕事を両立
- 「やりたい案件だけ選ぶ」という働き方でモチベーション維持
こうしたメリットに魅力を感じる若手会計士が増える一方で、いきなり独立するとスキル・信用・人脈が不足しがちなのも事実。そこで注目されるのが、「まず監査法人で経験値を積む」というキャリア戦略です。次の章では、フリーランスになる前に監査法人で学ぶべきことを具体的に解説していきます。
フリーランスになる前に監査法人で学ぶべきこと

フリーランスとして独立するには、実務スキルと信用の両輪が不可欠です。そのベースを築く場として、監査法人は非常に優れた環境です。現場での経験が将来の仕事の質を左右するからこそ、最初の数年間をどこでどう過ごすかが重要なのです。
監査現場で得られる“信用”と“スキル”
- 公認会計士としての看板だけではなく、「実務経験」こそが信用の源
- 上場企業や金融機関の会計処理を担う経験が、フリーランス時に顧客からの信頼を得る材料に
- 監査調書作成やヒアリング力、資料精査の精度がプロレベルに引き上げられる
被監査会社対応力と報告書作成の経験
- 経営層・経理担当者・法律顧問など、多様な関係者とやり取りするスキルが磨かれる
- 複雑な内容を“相手に応じた伝え方”に変換する力は、将来の提案型営業に活かせる
- 実際に報告書を書く経験が、のちに経営分析や資金調達支援にも直結
チームマネジメントと業務プロセスの理解
- スタッフ~シニアの期間に、チームでの役割分担や管理能力を実践的に習得
- スケジュール調整、進捗管理、後輩指導など、フリーになると独力で行うべきことの練習になる
- また、業務フローを標準化・改善する視点も自然と身につく
このように監査法人では、フリーランスとして“信頼される専門家”になるための土台を築くことができます。では、実際にその経験がどのように独立後の仕事に結びつくのか?次のセクションでは、監査法人での経験がフリーランスにどう活きるかを具体的に紹介していきます。
監査法人での経験がフリーランスにどう活きる?

監査法人での数年間は、単なる修業期間ではありません。実務を通して得た経験や信頼性の高さは、フリーランスとしての活動において強力な武器になります。ここでは、監査法人でのキャリアがどのように独立後の仕事に直結するかを解説します。
法人顧客との信頼構築がしやすい
- 監査法人出身というだけで、「この人はプロ」と感じてもらえるのが大きな利点
- 上場企業や大手企業との接点があることで、営業トークにも“実績”として活用可能
- 監査法人で得た名刺や人脈は、そのまま営業基盤にもなり得る
「元BIG4出身です」だけで信頼される現場があるのは、事実です。
業界全体の視野と横断的な知識
- 監査業務では、複数の業界・企業・ビジネスモデルを分析するため、自然と多業種に対応できる力が身につく
- 税務、会計、内部統制、経営分析など、広範な知識を統合して判断できる
- 複数企業の比較による“引き出しの多さ”は、独立後の提案力に直結
実務で鍛えられる問題解決力と提案力
- 監査では、トラブルや誤謬への対応、被監査会社への改善提案なども日常的
- 「どう伝えるか」「どこまで踏み込むか」を考える中で、高度なコミュニケーション能力と交渉力が養われる
- これは、フリーランスでのクライアント対応やアドバイザリー業務にそのまま活きる
監査法人で培った経験は、独立後に“信頼を得る力”“課題を見つけて改善に導く力”として再定義されます。次に、実際にフリーランス会計士がどのような仕事をして、どのような収入を得ているのかをご紹介します。
フリーランス会計士としての仕事と収入のリアル

独立後、フリーランスの会計士はどのような仕事をしているのでしょうか?監査法人を経験した後に独立する場合、どんな案件が得られ、どれくらいの収入になるのかは、気になるポイントです。ここでは、フリーランス会計士の実態に迫ります。
税務顧問・決算代行・経理支援の実情
- 最も一般的な業務は以下の通り:
- 中小企業やスタートアップの月次顧問業務
- 決算書作成・申告書作成(法人・個人)
- クラウド会計導入・経理業務のBPO(外注化)提案
- 特に最近では「経理業務のDX化支援」といった新しいニーズも増加
- 監査法人で得たExcelや会計ソフトの知識がそのまま活かせる場面も多い
月額顧問報酬は5万円前後から。複数社と契約することで安定した収入に繋がる。
案件獲得方法と営業活動の必要性
- 主な案件獲得チャネルは:
- 士業系マッチングサービス(例:ココナラ、税理士ドットコム)
- 監査法人時代の人脈・紹介経由
- SNSやnoteなどでの専門性発信
- フリーランスになると、自分を“売る”営業活動が必須。
- ポートフォリオやブログを作成し、「得意な分野」「経験」「料金表」などを明確化しておくと有利
「営業が苦手」は独立初期の壁だが、経験を積めば継続案件で安定してくる。
年収はどう変わる?収入モデルの一例
- 収入は大きく個人差あり。以下は一例:
- 月次顧問5社(各5万円)=月25万円
- 決算代行・スポット業務:年間150万円
- その他セミナー講師やnote販売等:年間50万円
- 合計で年収450〜600万円程度(独立初期の平均)
監査法人時代よりも“上がる人”もいれば、“下がる人”も。自分でコントロールできるのが最大の魅力。
フリーランスには自由もあれば責任もあります。しかし監査法人で得た経験とスキルがあれば、独立後の活動に大きな自信を持って臨めます。では、どのタイミングで監査法人を辞めるのがベストなのでしょうか?次章でそのヒントをお伝えします。
監査法人から独立するベストタイミングとは?

フリーランスとして独立するには、いつ監査法人を辞めるのが最適なのでしょうか?早すぎる退職にはリスクもありますし、遅すぎると独立の機会を逃す可能性もあります。ここでは、キャリアの分岐点としてのベストなタイミングを考えていきます。
修了考査合格後で辞める人の共通点
- 早期退職者には以下のような特徴があります:
- 将来的に独立を視野に入れた強い意志がある
- 業務内容に物足りなさを感じ、変化を求めている
- 個人で稼ぐための準備を着実に進めている(例:副業経験、SNS発信など)
- ただし、リスクも伴います。
- 独立後に「信用」が足りず案件が獲得できないケースも
- 「監査法人で何を得たのか」が曖昧だと職務経歴として弱くなる
2〜3年で辞めるなら、目的と計画をしっかりと持つことが重要です。
マネージャーまで残ることで得られるもの
- 一方で、監査法人に長く残るメリットも多いです。
- マネジメント経験や部下の育成力
- IPOやM&A、海外被監査会社などの希少な案件に関われる
- 被監査会社や上司からの信頼が蓄積される
- こうした経験は、フリーランス後の営業や提案活動で「圧倒的な信頼」を勝ち取る材料となります。
「マネージャー経験あり」は、独立後の名刺代わりになる武器です。
自分の市場価値を見極める3つの視点
- 今の業務で自分の強みが明確になっているか? → 会計だけでなく、人材管理、IT活用、改善提案など幅広いスキルを見直しましょう。
- 監査以外の経験・実績があるか? → 社内PJへの参加、他部門との連携、外部講師経験なども価値を高めます。
- “辞めた後に選ばれる人材”であるか? → クライアントや上司が「ぜひ独立後も仕事をお願いしたい」と思う状態が理想です。
独立はゴールではなく、スタートです。自分が市場でどう評価されるかを常に意識しましょう。
ここまで、監査法人からフリーランスへ転身する上でのステップや注意点を整理してきました。では最後に、この記事のまとめを通して、あなた自身のキャリアをどのように描いていけばいいのか確認してみましょう。
まとめ:フリーランスを見据えた監査法人キャリアの選び方

「監査法人を経てフリーランスへ」という選択は、単なる転職ではなく、会計士としての“価値”を最大化するための戦略のひとつです。
この記事を通じて、あなたは次のような視点を得たはずです。
監査法人からの独立が選ばれる理由を理解できましたか?
- なぜ会計士がフリーランスを目指すのか? → 自由な働き方、収入の上限がないこと、ライフスタイルに合わせた選択ができるから。
- そのために、監査法人で何を学ぶべきか? → 信頼、スキル、マネジメント能力、被監査会社対応力、そして全体視点。
- 監査経験は独立後にどう活きるのか? → 問題解決力、信頼構築、提案力といった「仕事を獲得できる力」になる。
- フリーランス会計士の実態はどうか? → 収入には幅があるが、自由度は高く、自分次第で大きく変化する。
- 独立するタイミングはいつが最適か? → 早期でも遅めでも正解はあるが、重要なのは「自分の価値」と「覚悟」の見極め。
フリーランスを目指すなら、まず監査法人で「信用」を築こう
会計士にとって、「数字が読める」だけでは不十分な時代です。
社会的信用や経験、人的ネットワークが、あなたの次のキャリアを支える土台になります。
その意味で、監査法人は単なる通過点ではなく、「信頼のブランド」としての価値を与えてくれる場所です。
若いうちに幅広い経験を積み、「どこでも通用する会計士」を目指すのは、最終的なフリーランス転身にも大きく活きてきます。
最後に:キャリアは一本ではなく、戦略的に描くもの
あなたが今、「監査法人に勤め続けるべきか」「将来はフリーランスとして活動してもいいのか」と悩んでいるとしたら――
それは非常に健全なことです。なぜなら、自分の将来を真剣に考えている証拠だからです。
しかし、焦って決める必要はありません。
今、得られる経験を着実に積み上げることが、結果的に最も自由で強いキャリアをつくる近道です。
監査法人でのキャリアは、あなたの可能性を広げる「最初の投資」。
その先にあるフリーランスとしての活躍を視野に、今できることからスタートしましょう。